 読者さま
読者さま観世水(かんぜみず)がどんな文様なのか詳しく知りたい!
どういう意味や由来を持っているの?
帯や着物に使われている文様は、それぞれに固有の意味や歴史を持っています。
「観世水」は流水文の一種で、川などの流れる水をイメージした渦巻き文様です。
室町時代から現在に至るまで多くの帯や着物に使われ、格調高い柄として愛されています。



観世水は帯や着物だけでなく、暖簾(のれん)や和雑貨などに使われることもある文様です。どこかで見かけたことのある方も多いかもしれませんね。
この記事では、流水文に込められた意味や、観世水文様の特徴や由来について解説します。
・流水文の意味
・観世水の由来と特徴
・観世水のコーディネート例
さまざまなアイテムに使われる観世水文様を深く知ると、きっと身につけてみたくなることでしょう。
それでは、ぜひ最後までお読みください。
観世水とはどんな模様?


古くから日本は水資源が豊かだったため、水はさまざまな文様の題材とされてきました。
「観世水」はそんな流水文の一種です。
この項目では、流水文の意味と、観世水文様の特徴や由来について解説していきます。
流水文の意味
流水文は、さまざまな器物や動植物と組み合わせて用いられることが多いモチーフ。
物語や歌の題材となる有名な川を表現するのにも、欠かせない存在です。
流水文には、以下の意味が込められています。
- 清らかさ(流れる水は腐らない)
- 魔除け(厄を流す)
- 火除け
流水文は、人びとの願いや祈りをモチーフにしたもの。
心身の浄化や清浄を願う「清らかさ」、災いや不安から身を守るための「魔除け」、火災から身を守るための「火除け」として、重宝されました。
流水文が長い年月にわたって使われてきたのは、まさにそうした人びとの想いに寄りそう存在だからこそなのでしょう。



水に関係のある文様は流水文だけではありません。波をモチーフとした青海波(せいがいは)や波頭(なみがしら)、滝モチーフの滝縞(たきしま)や滝文などもあります。
観世水の特徴とは?
観世水文様の特徴は、何本もの平行線を渦巻きや曲線でつないだ絵画的な水の表現です。
御所解文様(ごしょときもんよう)や茶屋辻文様(ちゃやつじもんよう)のように、風景をつなぐためによく使われます。
観世水は涼しい印象を与えるため、一般的に夏に着るものとされています。
ただし、桜や紅葉などと組み合わせている場合は、その植物に合わせた季節に着用するのがおすすめです。



桜と観世水なら春に、梅と観世水なら冬に着る、という感じですね。モチーフ化された植物や、季節感のない柄と組み合わせた帯の場合、一年を通して着用できますよ。
観世水は地味ながらも、他の柄や色との組み合わせ次第で帯の印象を大きく変える重要な文様です。
なお、観世水と同じ流水文の一種に光琳水という文様があります。
一見するとよく似た模様ですが、観世水と比べると光琳水はよりダイナミックな表現のモチーフです。
観世水の由来は能楽から
観世水の誕生には、観世稲荷社(京都府)の境内にある井戸が関わっているといわれています。
室町幕府3代将軍の足利義満が観阿弥・世阿弥に与えた屋敷には、名水と名高い井戸「観世井(かんぜい)」がありました。
この観世井に「龍が舞い降りて以来、つねに水面が渦を巻くようになった」という伝説から生まれた波紋が、観世水文様なのです。
能楽の衣装に使われていた観世水が、より注目されるようになったのは江戸時代の後期からです。
当時人気だった歌舞伎役者が観世水文様の舞台衣装を着た影響で、庶民にも大流行しました。
能楽をはじめとする芸能と関係が深い観世水は、舞台衣装だけでなく、着物や工芸品にも使われる模様です。
平安時代後期の写本「西本願寺本三十六人家集」の装丁にも描かれ、和歌に彩りを添えています。



一見地味な柄に見える観世水は、とても格調高い文様なんですよ。現在でも、色留め袖や袋帯の柄に使われています。
観世水のコーディネート一覧


シンプルな柄ゆえに、どんなコーディネートにもぴったりな観世水。
どんな着こなしをしているのかSNSから紹介しますので、参考にしてくださいね。
観世水の帯や着物のコーディネート例
まずは、着物や帯のコーディネート例からみていきましょう。
大きな満月とその中に描かれたススキ、そして観世水という組み合わせの帯。
一年でもっとも月が美しく見える中秋の名月に、ぴったりの着こなしですね。
同系色でそろえた帯と無地の着物から、秋にふさわしい大人の気品が漂っているようです。
黒字にぼやけた白い模様の入った小紋に、観世水を織り込んだゴールドの名古屋帯。
一見すると帯の中の観世水文様は目立ちませんが、着こなしに気品を添えているのが分かりますね。
着る時期を選ばない、素敵なコーディネートです。
どちらも水を表わす観世水と青海波の組み合わせに、桜楓文(おうふうもん)の着物。
桜楓文とは春に咲く桜と秋の楓を並べて描いた模様で、季節を選ばず着られる柄です。
本来、季節が異なる植物が同時に水の上を流れることはありえませんが、帯や着物ならば、一緒に楽しめますね。
観世水と石蕗(つわぶき)の葉を組み合わせたこちらは、夏の着物である絽(ろ)らしい涼しげな印象を与えます。
よく見ると、帯にも縦になった観世水がありますね。
補色関係にある青と黄色を取り入れたこのコーディネートは、夏のお出かけに大活躍しそうです。
小物類の観世水活用例
観世水を活かしたコーディネートは、帯や着物だけではありません。
落ち着いたゴールドとシルバーの、存在感のある観世水モチーフ小物類。
水をモチーフにした全体コーディネートを、キリッと引きしめます。
黒の布地に赤・白・金色の菊、そして観世水が織られた扇子入れ。
菊は秋冬の花ですが、デザイン化された模様なので一年を通して使えます。
どちらも縁起が良く格の高い文様のため、お茶会やパーティーでも活躍しそうですね。
歴史ある観世水を知って使いこなそう!
この記事では、観世水について解説してきました。
あらためて、おさらいしましょう。
観世水は流水文の一種で、水の流れを渦巻きと曲線で表した文様です。
- 水の流れを元にした文様
- 御所解文様や茶屋辻文様など、さまざまな柄に使われている
- 清らかさ、厄除け、火除の意味を持つ
観世水は格の高い文様であり、現在は袋帯や色留め袖によく使われます。
- 渦巻きと直線で水の流れを表現している
- 涼しい印象を与えるため、一般的には夏に着るもの
- 他の柄と組み合わせている場合、その柄に合わせた季節に着るのがおすすめ
また、観世水は、能楽を初めとする芸能と深い関係を持った文様です。
- 観世水は観阿弥、世阿弥の邸宅にあった井戸の伝説から生まれた文様
- 歌舞伎「小間物屋弥七」で舞台衣装に使われたことから、江戸時代に流行した
模様として使い勝手が良い観世水は、帯や着物はもちろん、それ以外の和雑貨などにも取り入れられています。
ぜひ日常生活に観世水を取り入れて、その涼やかな美しさを楽しんでみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

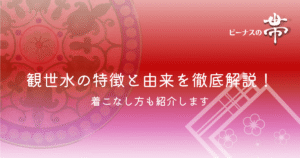
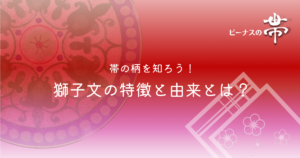
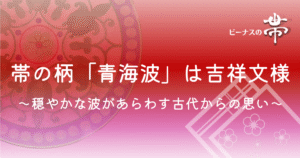

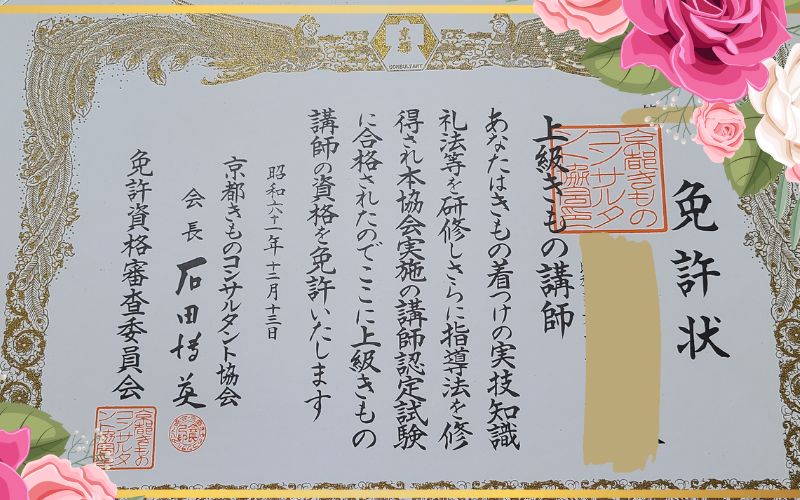

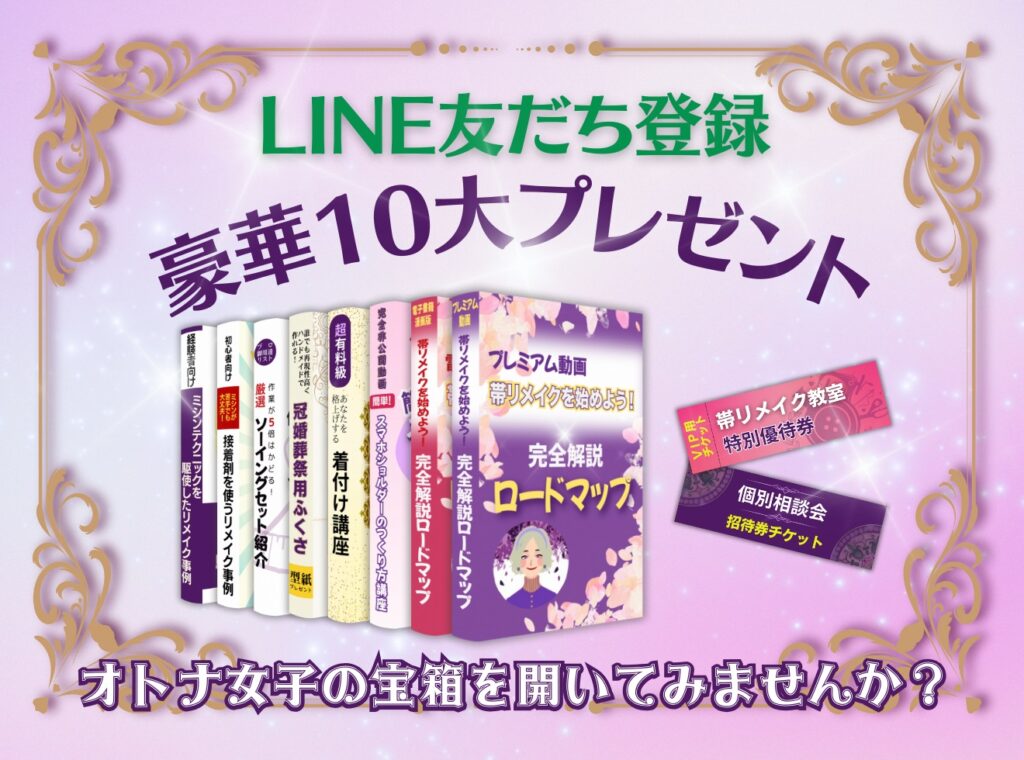



コメント