藍染めのやさしい色合いと、素朴ながら味わい深い絣模様。
愛媛県発祥の「伊予絣(いよがすり)」は、江戸時代から続く伝統的な綿織物です。
かつては庶民の普段着として親しまれ、今ではファッションや小物、インテリアとしても注目されています。
 読者さま
読者さま伊予絣って、どうやって作られているんですか?



伊予絣は、染め分けた糸で模様を浮かび上がらせて織られます。この工程で、独特の模様ができるんですよ。
この記事では、伊予絣のルーツや受け継がれてきた制作技法、そして現代の暮らしに活かすヒントを、画像とともに紹介します。
- 伊予絣の歴史的背景と誕生のルーツ
- 伊予絣の制作工程
- 伊予絣の魅力や楽しみ方
伊予絣の制作工程の奥深さや使いやすさを知ると、きっと日常に取り入れたくなるかもしれません。
ぜひ、最後までお読みください。
伊予絣とは?その歴史と受け継がれる背景


現在では、工芸品として親しまれている伊予絣。
時代の流れとともに形を変えつつも、一貫して人の手によって丁寧に織られてきました。
その歩みをたどると、地域の暮らしと密接に結びついた綿織物であることがわかります。
ここでは、伊予絣の誕生から現代までの歴史をひもときながら、どのように人々の暮らしに寄り添い、受け継がれてきたのかを見ていきましょう。
江戸時代に生まれた庶民の織物
伊予絣の起源は、江戸時代後期にまでさかのぼります。
当時の伊予地方(現在の愛媛県今治市周辺)では、農家の女性たちが自家用の木綿の着物や作業着を織り、仕立てていました。
そんななかで、新たな模様織りの技法を生み出したのが、鍵谷(かぎや)カナという女性です。
彼女は、藁(わら)屋根の押し竹にできた縄目の跡からヒントを得て、染め分けた糸で模様を浮かび上がらせる技法を考案。
これが伊予絣の始まりとされており、地元の人々の間で少しずつ広まっていきました。
「藍染めの深い色合いとにじんだような独特の模様」の織物は、丈夫で長く使えるため、庶民の普段着や作業着として重宝されるようになります。



伊予絣は、実用的で庶民の暮らしに根づきながら受け継がれてきた織物。当時の人々の知恵と工夫が、今に伝わっているんですね。
明治〜昭和の発展と全国への広がり
明治時代になると、伊予絣はより広く知られるようになり、産業としての発展をとげます。
地域に織元や工房が増え、絣模様のバリエーションも豊かになり、実用性だけでなく美しさも兼ね備えた織物として評価されていきました。
この時期、「丈夫で洗っても型崩れしにくい」という伊予絣の特徴が注目され、学校の制服などにも広く使われるようになります。
とくに大正から昭和初期にかけては、「長持ちする織物」として全国的に普及しました。
しかし、昭和の高度経済成長とともに生活スタイルが洋装中心に変化すると、和服や絣織物の需要は徐々に減少していきます。
それでも伊予絣は、地域の人々の手によって大切に守られ、受け継がれてきたのです。



時代を超えて評価された理由は、なによりも伊予絣の丈夫さや実用性によるところが大きいでしょう。
現代の伊予絣と継承の取り組み
伊予絣は、かつての生活に根ざした織物から、伝統工芸としての価値が見直される存在となりました。
近年では、職人の高齢化や後継者不足といった課題があるいっぽうで、技術の継承と魅力の発信に取り組む動きも各地で進んでいます。
たとえば、今治市を中心に、以下のように伊予絣の継承を目的とした取り組みが行われています。
- 見学や体験ができる工房の整備
- 若手職人の育成支援
- 地域イベントでの展示 など
また、洋服やバッグ、インテリア雑貨など、現代のライフスタイルに合わせた商品開発で、伊予絣の魅力を伝える試みもされるようになりました。
こうした活動によって、伊予絣は再び注目を集めつつあるのです。



伝統を守りながら、現代の暮らしに寄り添う伊予絣の新しい広がりが期待されますね。
伊予絣の制作工程


伊予絣の美しい模様は、熟練の職人による計算された手作業が集約されています。
ここでは、伊予絣がどのような工程を経て完成するのかを、みていきましょう。
伊予絣はどうやってできる?
一つひとつの手仕事で丁寧に作られる伊予絣。
その工程は大きく分けて、以下のような流れで進められます。
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 1. 絣図の作成 | 模様の設計図を描く |
| 2.括り(くくり) | 糸の一部をしばって染料を防ぐ。模様のもとになる工程 |
| 3. 染色 | 藍などの染料で染める。括った部分は白く残る |
| 4. 括りを解く | 括りを外し、模様が浮かび上がる |
| 5. 糊付け・乾燥 | 糸に張りをもたせるための下準備 |
| 6. 整経 | 経糸(たていと)を織機用に並べる準備 |
| 7. 管巻き | 緯糸(よこいと)をボビンに巻く |
| 8. 機がけ | 織機に糸をセットする |
| 9. 織り | 手織りまたは機械織りで布を織る |
| 10. 仕上げ | 湯通し、幅出しなど風合いを整える工程 |
これらの工程は、それぞれに職人の経験や技術が必要です。
とくに、次の項目で紹介する「括り」や「染色」は、伊予絣の模様の良し悪しを決定づける大切な要素になります。
特徴的な模様をつくる「括り(くくり)」と「染色」
伊予絣の象徴ともいえる模様は、「括り」と「染色」という二つの工程から生まれます。
まず行うのは「括り」です。
絣図(かすりず)と呼ばれる設計図にそって、白い糸の一部を糸やビニールなどで丁寧にしばっていきます。
これは糸を染色する際に、その部分へ染料が染み込まないようにするための工程。
糸が染まった部分と染まっていない部分で模様をつくる、重要な部分です。
括る位置や、幅のわずかな違いが仕上がりに大きな影響を与えるため、高い集中力と職人の熟練した感覚が欠かせません。
続く「染色」の工程では、括った糸を藍(あい)で何度も染め、乾かし、また染めるという工程を繰り返します。
時間をかけて色を重ねていくことで、深みのある独特の色合いが生まれるのです。
すべての工程が終わったあとに括りをほどくと、染まらなかった部分が白く残ります。
染め終わった糸を機にかけると、模様がきれいに出ているのがわかりますね。



図案の模様を再現するためには、括りの精度、染めの深さ、糸の扱いすべてにおいて高い技術が求められるのですね。
時間と労力を要する「織り」
伊予絣の多くの工程のなかでも、もっとも時間と労力を要するのが「織り」の工程です。
機織りは、織り手の技術によって仕上がりが変わってくるため、熟練した職人の技術と豊富な経験が必要になります。
かつてはすべて手織りで行われており、夜通し機を踏み続けても、1反(約12m)を織りあげるのに1週間かかるほどでした。
大正時代に足踏み式の織機が導入されると、1反を2〜3日で織れるようになり、生産効率が大きく向上します。
さらに昭和以降、動力織機の普及によって、1日に2反程度を織ることも可能になりました。
とはいえ、織りの工程は、糸の準備から模様をずらさずに仕上げる細かな調整など、時間と技術を要することに変わりありません。



1反の織物には、工程ごとに積み重ねられた手間と、職人の経験によるこまやかな技術が込められているのです。
伊予絣を生活に取り入れる方法


伝統的な織物というと「格式が高くて日常では使いにくそう」と思われがちですよね。
伊予絣はカジュアルな素材なので、現代の暮らしと相性がよく、さまざまな形で楽しめます。
ここでは、伊予絣をもっと身近に取り入れる方法を紹介します。
服:伝統的な和装から日常のファッションまで
伊予絣は、着物や作務衣といった和装にとどまらず、現代のファッションにも柔軟に取り入れられています。
着物や帯を使った洋服リメイクもたくさんあり、どれも伊予絣を身近に感じられるものばかりです。
こちらは絣模様が印象的な着物コーディネート。
藍と白のコントラストが美しく、モダンな雰囲気も感じさせます。
帯との組み合わせも粋で、伝統を楽しむ大人の着こなしです。
こちらは、藍色が綺麗なリメイクコートワンピース。
スカート部分に模様の異なる伊予絣が使われています。
まさに伝統的な和のテイストと現代的な感覚の融合ですね。
黒地にカラフルな模様が映える遊び心あるワンピースは、ストライプ柄のポケットがアクセント。
伊予絣の可能性を広げる楽しいアレンジですね。



伊予絣は木綿の織物なので、日常的に着れる気軽さがあります。伝統を大切にしながらも、自分らしいスタイルに取り入れて楽しめるのが大きな魅力ですね。
小物:バッグや財布にさりげなく和の風合いを
もっと気軽に伊予絣を楽しみたい方には、バッグやポーチ、財布などの小物類がおすすめです。
日常的に使う小物に伊予絣を取り入れることで、ふとした瞬間に伝統の美しさに触れられるのも嬉しいポイント。
旅先でのお土産や贈り物としても人気があります。
柔らかなグレー地に縞模様が映える、ナチュラルな雰囲気のポーチ。
さりげなく伊予絣を取り入れたい方にぴったりのアイテムですね。
コスメやアクセサリー入れとしても重宝するでしょう。
深みのある藍に細かな模様が浮かぶ、クラシカルながま口タイプの財布。
手のひらになじむサイズ感が、伊予絣の可愛らしさを引き立てます。
こちらは伊予絣を使用したティッシュケースです。
カバンの中にひとつ入っているだけで、気分がふっと和らぐような存在感がありますね。



丈夫で実用的な伊予絣の小物類は、贈り物や日常使いのアイテムとしても高く評価されています。
インテリアアイテム:暮らしに和のアクセントを
伊予絣の持つ落ち着いた色合いや素朴な風合いは、暮らしの空間にもやさしくなじみます。
座布団やのれんなどのインテリアアイテムに取り入れて、和の美しさと温もりを日常に添えましょう。
藍染めならではの深い色合いに、伝統的な絣模様がほどこされた座布団。
木の家具などの自然素材と調和し、空間に静かな上質感をもたらします。
実用性とデザイン性を兼ね備えた、暮らしの中のささやかなぜいたくですね。
こちらは伊予絣ののれんです。
伝統的な文様とやわらかな色調が、空間をやさしく仕切るとともに、訪れる人をあたたかく迎え入れてくれます。



インテリアとして日常の中にさりげなく取り入れることで、穏やかな時間と心のゆとりを与えてくれる存在にもなりますね。
伊予絣の魅力と今の暮らしへのつながり
この記事では、伊予絣の基礎知識から制作の流れ、現代の暮らしに取り入れるためのヒントを紹介しました。
あらためて、伊予絣のポイントを振り返ってみましょう。
- 江戸時代後期に、愛媛県今治市で生まれた絣織物
- 鍵谷カナが考案した「括り」と「染色」の技法が起源
- 庶民の普段着や仕事着として親しまれてきた
伊予絣は、古くから庶民の生活に密着した絣織物です。
丈夫で洗っても型崩れしにくいことから重宝され、全国に普及しました。
- 明治以降、実用性の高さから全国へ普及
- 昭和の洋装化で需要が減少するも、地元で継承の努力が続く
- 現在は工芸品・文化財として再注目されている
伊予絣の模様や美しさは、制作にかかる労力や細やかな職人技によって生まれます。
- 工程は10以上
- 「括り」と「染色」はもっとも重要な工程
設計図に合わせて染めない部分を括り糸でしばり、何度も染料につけることで、伊予絣独特の模様ができあがるのです。
現在、伊予絣は伝統を守りつつ、現代のライフスタイルを柔軟に取り入れ、さまざまなアイテムを展開しています。
- 洋服リメイクなどに応用
- ポーチやがま口財布、ティッシュケースなどの小物
- 座布団やのれんなどのインテリア
時代の変化を経てもなお、地域に根ざして受け継がれてきた伊予絣。
日常の中でその魅力に触れることで、伝統工芸の奥深さや、手仕事の温かみを感じていただけることでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


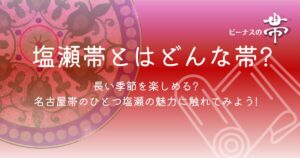
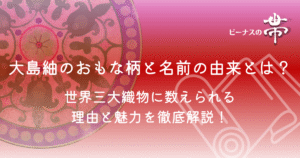

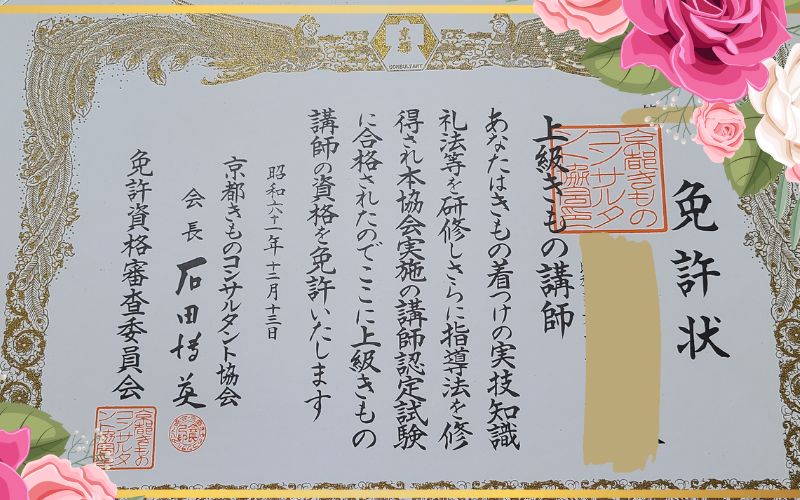

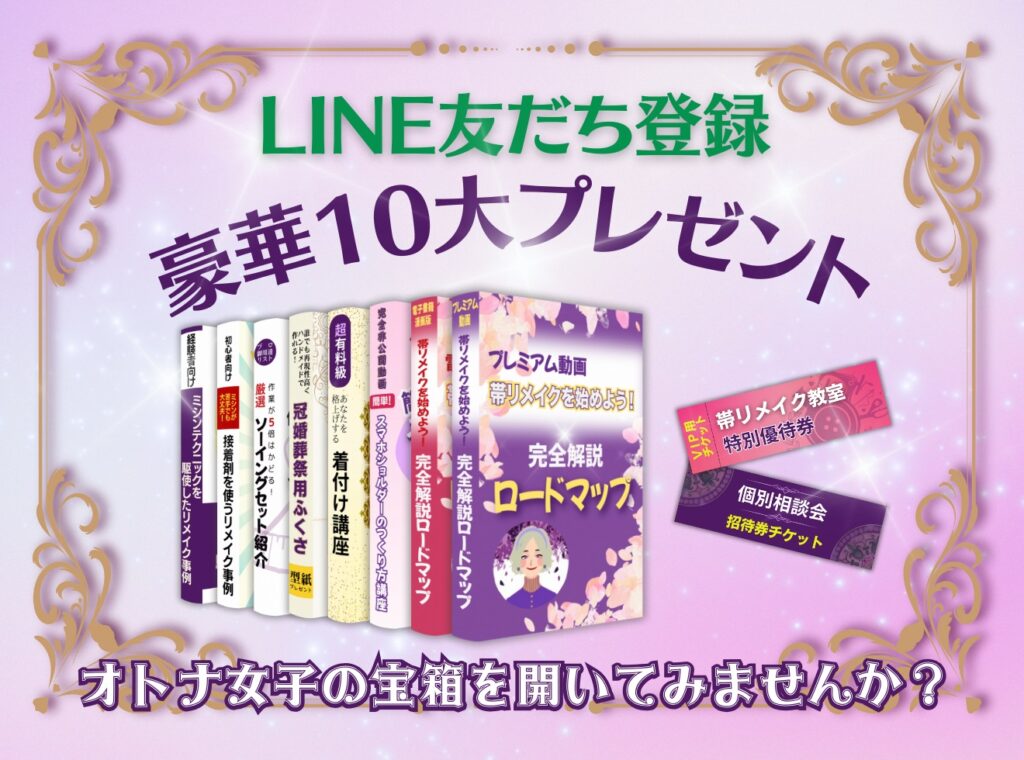
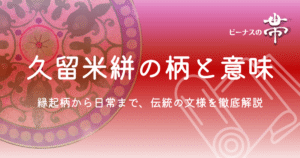
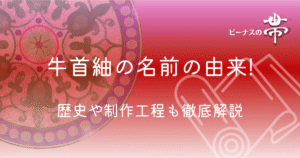
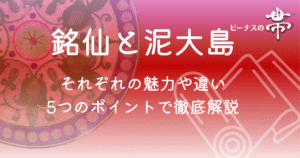
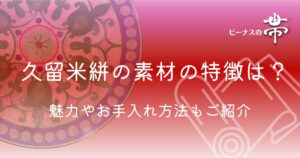

コメント