 読者さま
読者さま手持ちの古い帯が銘仙らしいけど、どの産地の銘仙なのかわからない……。
親が遺した古い帯や若い頃に購入した帯が、どこの産地で織られた銘仙か知りたいですよね。
銘仙の産地は、足利・桐生・伊勢崎・秩父・八王子の5つが有名です。
銘仙は独特な風合いでカラフルな模様が多いのが特徴で、かつて全国で生産されていました。
大正時代から昭和初期にかけて普段着として普及し、現在はアンティーク和装として人気があります。



今回は、銘仙の歴史や特徴とあわせて、五大産地ごとに銘仙を見分けるポイントを解説しますね!
そのほかにも、古い銘仙の帯や着物を捨てることなく活用する方法も紹介します。
- 銘仙の歴史と特徴
- 産地ごとの銘仙の見分け方
- 古い銘仙の帯や着物の活用方法
この記事を読めば、銘仙の産地が特定できるようになり、愛着がわくかもしれません。
ぜひ最後までお読みください。
銘仙って何?特徴と歴史について


着物といえばフォーマルな場で着るイメージがありますが、銘仙はかつて普段着やオシャレ着として大流行した着物です。
この章では、現代でもアンティークとして人気の銘仙の特徴と歴史を解説します。
銘仙の特徴
銘仙は絣(かすり)という技法で織られた、平織りの絹織物です。
平織りは縦横の糸が1本ずつ交互に重なっていて、生地が頑丈なため、ガーゼや帆布に使われてきました。



着物では銘仙の他に、ちりめん、羽二重などが平織りで作られています。
経糸(たていと)と緯糸(よこいと)をわざとずらして織った結果できる、ぼやけた輪郭の柄が銘仙の特徴です。
- 平織りなので丈夫
- 軽くて着心地がよい
- 大胆な柄のものが多い
- 絹織物に特有のなめらかさがある
- ぼやけた輪郭の柄
銘仙の優しい雰囲気と模様は、この絣手法によって生まれたものなのです。
銘仙の歴史
銘仙が生まれたのは江戸時代後期のこと。
関東・中部地方の養蚕農家が、他の絹織物に使えない玉糸や屑糸で織った着物が銘仙の原点です。
当時の銘仙は養蚕農家が自家用に作っていたものですが、着心地の良さと丈夫さが人気になり、庶民の間に広まっていきます。



当時の銘仙は主にはんてん、布団、女学生の普段着に使われていました。
明治時代まで、銘仙といえば縞柄が一般的でしたが、大正時代以降は技術が多様化し、縞柄以外の模様が多く作られるようになりました。
また、大島紬やお召(めし)を真似することで、銘仙を作る技術が発達します。
その結果、モダンなデザインと絣の優しい風合いが合わさって、銘仙は独自の個性を持つ着物となったのです。
しかし、第二次世界大戦後は、手入れが簡単で安価なウールの着物や洋装の人気に押され、銘仙は消滅の危機を迎えます。
そして、1990年代後半のアンティークブームの到来により復活し、新たな銘仙が作られるようになりました。
産地ごとにみる銘仙の特徴と見分けるポイント


銘仙の産地といえば、足利(栃木県)・桐生(群馬)・伊勢崎(群馬県)・秩父(埼玉県)・八王子(東京都)の5つ。
それぞれに織手法が違うので、色や柄のぼやけ方で産地が特定できます。
ここでは、五大産地ごとの特徴と見分け方を紹介するので、ぜひ手持ちの帯や着物と比べてみてくださいね。
足利銘仙の特徴と見分けるポイント
足利銘仙が生まれた栃木県足利市はほぐし織り発祥の地。
銘仙が生まれる以前から、養蚕と織物の産地として栄えた場所でもあります。
足利銘仙は、養蚕地としてのノウハウを活かして大量生産をしたため、銘仙の中では手ごろな値段で取引されていました。
こちらは銘仙の特徴である、ポップでカラフルな足利銘仙です。
この足利銘仙は、シンプルな青と黒の格子模様が素敵ですね。
足利銘仙は日本で最も生産されている銘仙で、デザイン性が高く、半併用絣(はんへいようかすり)の技法で織られています。
半併用絣とは経緯絣(たてよこがすり)の一種で、足利で開発された技法です。



型紙で模様を染めた経糸と部分的にしぼって染めた緯糸を組み合わせて、模様のまわりを白く浮かび上がらせる技法です。
柄がスポットライトをあてたよう見えるのが、半併用絣の特徴ですね。
- 柄の周囲が白色になっている
- デザイン性の高さ
- 値段の手頃さ
桐生銘仙の特徴と見分けるポイント
桐生は「西の西陣、東の桐生」「織都(しょくと)桐生」と言われる織物の産地です。
こちらの桐生銘仙は、赤と黒のコントラストが目を引くデザインですね。
桐生銘仙の特徴は、1977年に国の伝統工芸品に指定されるほどの高いクオリティと、柄や模様が細かい点です。
お召と同じく高品質のより糸を使用しているため、「お召銘仙」とも呼ばれています。



お召は、江戸幕府第11代将軍の徳川家斉が好んだとされる生地です。
現在では、略礼装やおしゃれ着に使われます。
ただし、他の地域と比べると生産量が少ないため、場合によっては桐生市を銘仙の生産地に含まないこともあります。
- 細かな柄・模様
- 高品質な糸
伊勢崎銘仙の特徴と見分けるポイント
群馬県伊勢崎市の伊勢崎銘仙は、江戸時代に養蚕農家が着ていた太織(ふとおり)から生まれた織物です。
精巧な絣を織る技法が開発されたことから、明治時代から昭和にかけて多くの人に着られていました。
伊勢崎銘仙の特徴は併用絣(へいようがすり)によるあざやかな色と、模様の多様性です。



併用絣と半併用絣の違いは、模様の周りにある白い染め残しの有無です。
半併用絣は緯糸をしぼった部分が白く浮かびあがりますが、伊勢崎銘仙に使われる併用絣は、同じ色に染めた経糸と緯糸を使用します。
そのため伊勢崎銘仙は、あざやかな色彩の模様が多いんですよ。
併用絣は、経糸と緯糸の両方に柄や色をつけて織る技法。
5つの産地の中でも伊勢崎でしか作れないと言われるほど、難易度の高い織り方です。
優しい風合いがかわいらしい伊勢崎銘仙です。
花などの植物をはじめとして、さまざまな模様がありますね。
伊勢崎銘仙の模様や織り目がよく分かる写真ですね。
- あざやかな色
- 柄や模様の多様さ
秩父銘仙の特徴と見分けるポイント
秩父銘仙の特徴は、ほぐし捺染(なっせん)という技法を使って糸を染めている点です。



捺染とは染色技法のひとつです。別名で型付け、型染めとも呼ばれています。現代では、機械を使用して染めることもあります。
秩父銘仙のほぐし捺染は、織る前段階の経糸に型を当てて染めていきます。
そのあと、本織りの段階で経糸を手でほぐしながら緯糸を入れ直すため、「ほぐし捺染」と呼ばれるようになりました。
色が異なる経糸と緯糸を組み合わせるため、布地に玉虫色のような光沢がみられます。
落ち着いた紫色に、植物の模様がシックな秩父銘仙。
どんな着物になったのか、みてみたいですね。
こちらの秩父銘仙は赤紫の花柄がかわいらしいですね。
若々しさにあふれています。
- それぞれ異なる色の経糸と緯糸
- 玉虫色の光沢
八王子銘仙の特徴と見分けるポイント
東京都八王子近郊で生まれた八王子銘仙は、カピタン織りという技法で織られています。
カピタン織りは細やかな織りが特徴の織り方で、このカピタン織りによって、八王子銘仙は細かい凹凸(地紋)のある生地に仕上がります。
レトロな雰囲気のある八王子銘仙。
アンティークな背景にもよく似合いますね。
濃いピンクに黄色いバラ模様が印象的なこちらの銘仙。
画像をよく見てみると、八王子銘仙特有のこまかい凹凸がはっきりと分かります。
かつて桑都(そうと)と呼ばれた養蚕の名地・八王子ですが、戦後になるとウールに取って代わられてしまいました。



現在、銘仙の生産は行われていませんが、カピタン織りの技術はネクタイ等の小物に活かされています。
- 細かい地紋によって生まれる風合い
古い銘仙の帯を活用する3つの方法


日常的に着物を身につける機会がなく、着物や帯が古いからといって捨てるのは、なんとも惜しいですよね。



古い帯でも銘仙は根強い人気があるんですよ。捨ててしまう前に、いま一度活用できないか、検討してみましょう。
そこでこの章では、古い銘仙の帯や着物を活用する方法を紹介します。
活用方法は3つあります。
古い銘仙の帯や着物を活用する方法
- 自分で着る
- 小物にリメイクする
- 買取業者に引き取ってもらう
それぞれみていきましょう。
自分で着る
まずは、銘仙を着てみましょう。
着物や帯の型は変化が少なく、洋服と比べると流行に左右されにくい傾向があります。
銘仙には、現代の和服にはないアンティーク独特の魅力があるのです。
アンティークな帯の魅力
- 歴史的な価値や思い入れがある
- 現在では生産していない独自のデザインがある
- 個性と特別感がある
帯と着物がどちらも赤・白・黒の3色でそろえられていますね。
統一感のある着こなしです。
銘仙の着物と帯をコーディネートしたこちらの写真。
銘仙特有のレトロな雰囲気が、より引き立ちますね。
もともと銘仙は、普段着や気軽なお洒落着として作られていたため、日常的に着用しやすい着物です。
洋装とのコーディネートも楽しめるので、一度は着てみるのもおすすめ。
着物や帯の汚れがひどい場合は、専門のクリーニング店に相談してみましょう。
リメイクして小物を作る
状態が良ければ、リメイクするのも活用法のひとつです。
汚れたり破れたりしている部分を避ければ再利用が可能なので、古い帯で小物を作ってみてはいかがでしょうか。
リメイクすれば日常的に活用できるので、ぜひ参考にしてくださいね。
それぞれ、個性豊かな銘仙の模様を上手に生かしたリメイクです。
使う柄の部分やアイテムによって表情が変わるのも、銘仙ならでは。
愛着のある帯を日用品として使えるだけでなく、小物であれば保管スペースが少なくて済むのがリメイクのメリットです。
リメイクで作りすぎたら、フリマサイトやオークションサイトで販売してもいいでしょう。
なお、帯や着物にハサミを入れると、元の形に戻せません。
小物にリメイクするときは、カットしても惜しくないものを選んでくださいね。
買取業者に引き取ってもらう
着物や帯を扱っている買取業者に引き取ってもらう方法もあります。
古いものでも引き取ってリサイクルにまわしてくれるので、環境貢献にもなるでしょう。
買取方法は、出張買取・店頭買取・宅配買取の3種類があります。
こちらはそれぞれのメリットとデメリットです。
| 買取方法 | メリット | デメリット |
| 出張買取 | ・店に帯を持ち込まなくていい | ・自宅が対応エリア内にない可能性がある ・スケジュールの調整が必要 |
| 店頭買取 | ・すぐに現金を受け取れる ・プロと相談しながら取引可能 | ・店舗が近くにないことがある ・大量の帯を店舗まで運ぶのが大変 |
| 宅配買取 | ・直接のやり取りが不要 ・業者のスケジュールに左右されない | ・値段の交渉がしにくい |
上表を参考に、自分に合った方法で取引をしてくれる買取業者を選びましょう。
また、買取業者の中には着物や帯を扱っていても、専門知識を持っていない業者も存在します。
帯に詳しくない業者に依頼してしまうと、本当の価値よりも低く買い取られてしまうかもしれません。
事前に買取価格の相場を調べたり、業者のWebサイトやクチコミなどで評判を調べておくと安心ですね。



買取業者や買取方法をしっかりと調べておくことで、悪質な業者の被害にあう確率を減らせます。複数の業者に見積もり依頼をして、比較検討しましょう。
こちらの記事ではおすすめの着物買取サービスについて、ランキング形式でまとめてあります。
銘仙の帯や着物を売りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。


銘仙について知り古い帯を有効活用しよう
この記事では、産地ごとの銘仙の特徴と見分け方、古い銘仙の帯を活用する方法について解説してきました。
銘仙の特徴は以下のとおりです。
- 平織りで丈夫
- 軽くて着心地がよい
- 大胆な柄のものが多い
- 絹織物に特有のなめらかさがある
- ぼやけた輪郭の柄
もともと銘仙は、養蚕農家が普段着や作業着に作っていたのが、大正時代から昭和の初めまで流行していました。
関東地方の足利、桐生、伊勢崎、秩父、八王子が特に有名な銘仙の産地です。
産地ごとに異なる銘仙の見分け方をおさらいしましょう。
| 種類 | 産地 | 特徴 |
| 足利銘仙 | 栃木県足利市 | 柄の周囲が白っぽい 高いデザイン性 手ごろな値段 |
| 桐生銘仙 | 群馬県桐生市 | 細かな柄・模様 高品質な糸 |
| 伊勢崎銘仙 | 群馬県伊勢崎市 | あざやかな色彩 多様な柄や模様 |
| 秩父銘仙 | 埼玉県秩父市 | 異なる色の経糸と緯糸による光沢 |
| 八王子銘仙 | 東京都八王子市 | 凹凸のある生地 |
このように、それぞれ特徴があることをお伝えしました。
また、親の形見や昔に買った銘仙を身につける機会がなくても、古い銘仙の帯を活用する方法はあります。
- 自分で着る
- バッグや小物にリメイクする
- 買取業者に引き取ってもらう
このなかから、あなたに合った活用方法をみつけましょう。
近年では着物好きの若者や、日本文化に興味を抱く外国人から人気を集める銘仙。
しかし、後継者不足などの問題もあり、今後は入手するのが難しくなるかもしれません。
アンティークな銘仙には、新しい帯や着物にない魅力があります。
古いからと捨ててしまう前に銘仙のことをよく知り、もう一度役立ててみましょう。
身につけたり飾ったりすることで、新しい発見があるかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
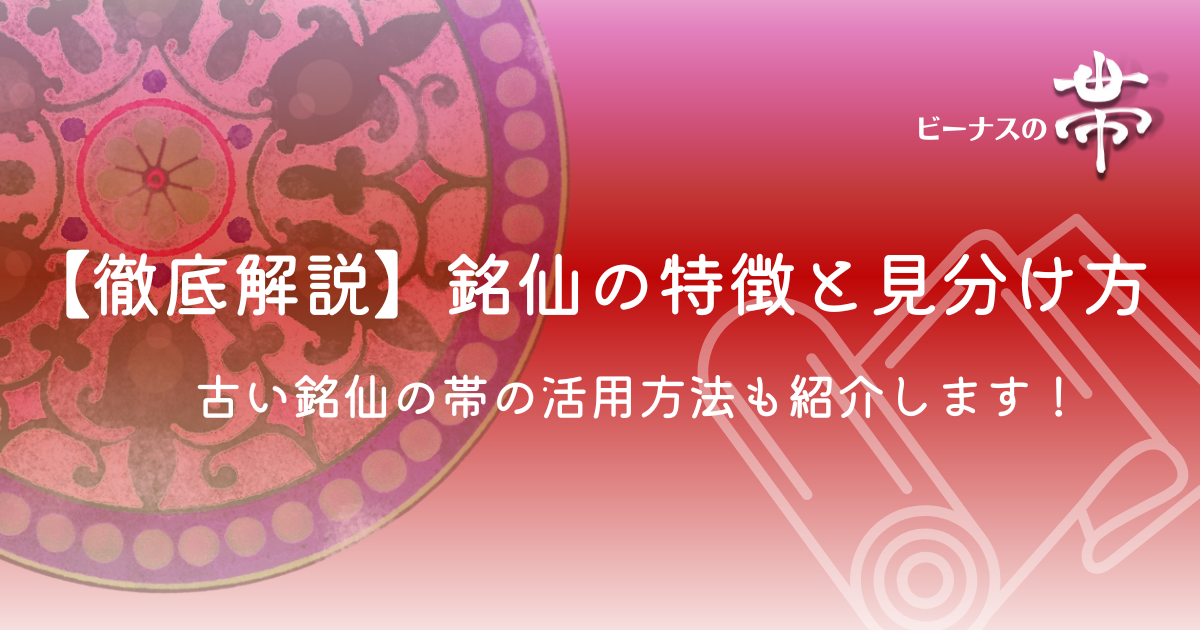

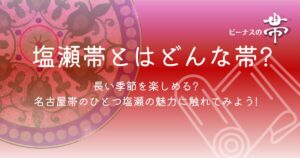

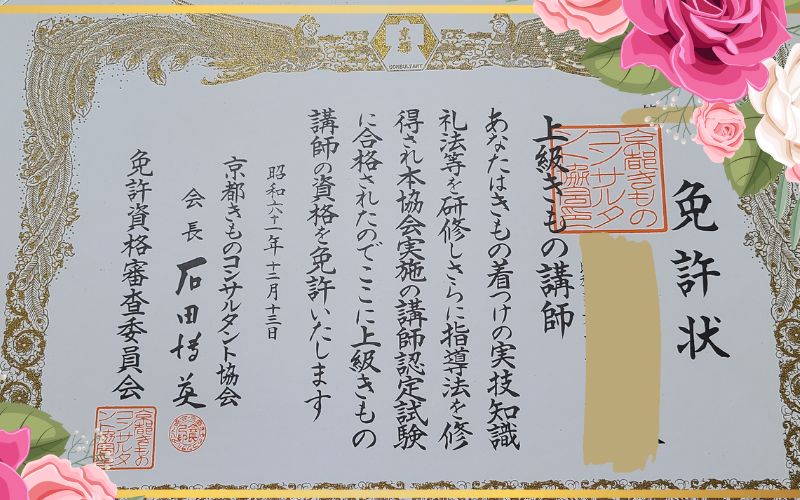

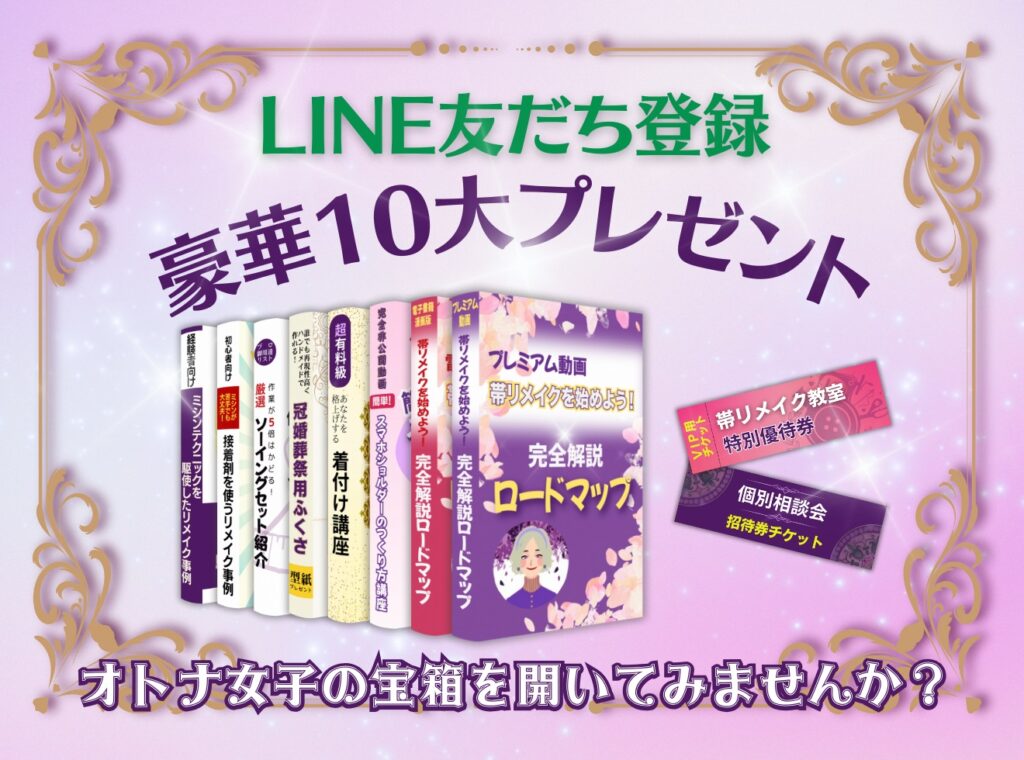
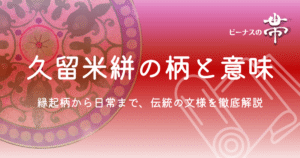
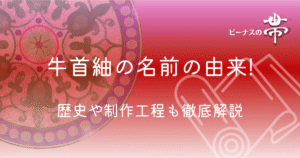
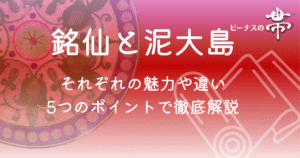
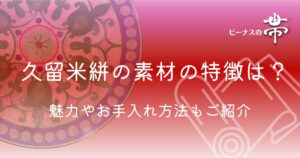
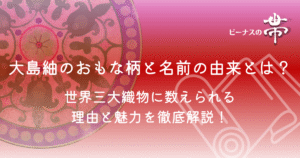

コメント