 読者さま
読者さま帯揚げがなくても着物は着れますよね?
どのような役割があるんですか?
着物を着たときに、帯の上からちらりと見える布が帯揚げです。
シンプルな単色から華やかな模様まで、実にさまざまなものがあります。
着物を着るうえで、帯揚げは必須のアイテムというわけではありません。
しかし、帯揚げを付けるか付けないかで、着物の印象が変わってきます。
この記事では帯揚げの歴史と役割、シーン別の選び方を詳しくお伝えしていきます。
- 帯揚げの歴史と役割
- 帯揚げの選び方
- 帯揚げの代用品



この記事を読むと、帯揚げの役割が理解でき、TPOに合わせた選び方を楽しめるようになりますよ。
ぜひ最後までお読みください。
帯揚げが生まれた背景と役割


実は、着物の帯は昔から今のような形状だったわけではありません。
現在の形になったのは、帯揚げが登場した同時期の江戸時代末期といわれています。
この章では、帯の変化とからめながら、帯揚げが生まれた背景と役割を見ていきましょう。
帯揚げの歴史
帯揚げの歴史は、帯の変化ととても深い関係があります。
もともと腰ひもで固定するだけだった帯は、時代とともに現在の形になり、その過程で帯揚げが生まれたのです。
帯揚げが登場するまでの流れを、大まかにまとめました。
帯揚げが登場するまでの流れ
・腰ひもで固定するのみの機能的な役割が中心
・装飾的な要素はない
・帯の幅が少し広くなり、平ぐけ帯で着物を留める
・染色技術の発展によって装飾的な要素が加わる
・細めの帯で着物を留めるのが主流
・豪華な装飾を好む文化の発展でより華やかになる
・遊女は華やかな名護屋帯を結んでいた
・さらに帯が幅広くなる
・深川の芸者が太鼓橋の完成を祝って「お太鼓結び」を考案
・帯揚げが登場する
幅広の帯が生まれたのは江戸時代に入ってからです。
始まりは遊女たちの帯といわれており、江戸時代の中頃には現在の帯の原型といえるほどの幅になりました。
そして江戸時代の末期頃、「お太鼓結び」が考案された際に、帯枕を包み隠し、帯結びの形を整えるために帯揚げが生まれたとされています。
明治時代には、一般の人も帯揚げを日常的に使用するようになりました。
明治以降は帯まわりを華やかに見せる「ファッション小物」としての意味合いが強くなっていきました。
帯揚げの役割
帯揚げは、機能面と装飾面の両方で着物の美しさを支える重要な役割があります。
機能面と装飾面におけるそれぞれの役割は、こちらです。
- 帯と着物の間に見える紐やすき間を隠す
- 帯枕(おびまくら)を包み込み、帯結びの形を安定させる
- 帯の上から少し見せることで、着物の印象を引き締め、華やかさを加える
- TPOに合わせた帯揚げ選びができ、おしゃれのアクセントとして楽しめる



どちらも、着物姿をきれいに見せるポイントとして欠かせない役割ですね。現在では、装飾的な役割が強くなっています。
帯揚げの選び方


帯揚げには、以下のようにさまざまな種類の素材が使われています。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 綸子(りんず) | 光沢のある柔らかく薄い生地 |
| 縮緬(ちりめん) | 染の色や柄がはっきりとしたやや厚めの生地 |
| 絞り(しぼり) | 正絹に絞りを施したボリュームのある生地 |
| 絽(ろ) | 夏用の正絹生地 |
| 紗(しゃ) | 透け感のある夏用の生地 |
| 麻(あさ) | 涼しげな麻の生地 |



フォーマルやカジュアルなどのシーンによって、帯揚げの素材を変えるのが一般的です。
ここでは帯揚げの選び方を、下の3つのシーンに分けて解説します。
- フォーマル
- セミフォーマル
- カジュアル
それぞれ見ていきましょう。
フォーマル
結婚式や入学式などのフォーマルなシーンでは、控えめで上品な帯揚げを選びましょう。
| シーン | 着物 | 帯揚げの選び方 |
|---|---|---|
| 結婚式・式典など | 留袖・訪問着・付け下げ | 基本的には無地の白・金・銀のみ 綸子・総絞り・紗 振袖には総絞りの帯揚げで華やかに |
フォーマルな着物や帯に合わせた帯揚げが、さりげなく着物の上品さをアップしてくれます。
セミフォーマル
高級レストランでの食事会や子供の入学式などのシーンでは、派手すぎず上品な印象を大切にしましょう。
| シーン | 着物 | 帯揚げの選び方 |
|---|---|---|
| 結婚式の招待客・食事会など | 色無地・付け下げなど | 綸子・無地の縮緬 絞りや淡い色の刺繍のもの 華やかすぎないもの |
絶妙なバランスのピンク系配色が、落ち着いた華やかさを演出しています。
カジュアル
お友達とのランチやショッピングなどに着物を着ていくときは、自分らしさを出してみましょう。
| シーン | 着物 | 帯揚げの選び方 |
|---|---|---|
| お茶会・ショッピングなど | 訪問着・小紋・絣(かすり) 紗や絽の夏物 | 縮緬・部分絞り・総柄 ポップな柄や鮮やかな色 濃い色の帯揚げ |
帯揚げが着物のアクセントになっていて、とても素敵です。
帯揚げの代用品





帯揚げを身近なもので代用できると嬉しいんだけど…
着物に合わせて帯揚げを変えるといっても、帯揚げを何本も用意するのは大変ですよね。
特にカジュアルな着物の場合、身近なもので個性を出すのにも役立つことでしょう。



身近なものでできる代用品を紹介しますね。
- スカーフ、ストール
- 手ぬぐい
- はぎれ
ひとつずつ解説していきます。
スカーフ、ストール
タンスに眠っているスカーフや薄手のストールを、着物に合わせてみてはいかがでしょう。
スカーフやストールほどの大きさがあれば、切ったりせずにそのまま帯揚げとして代用できます。
今日のお着物は、
— クロ (@4jQzeor5qudMvGH) October 21, 2021
ほぼ戻橋さんのフリマでお家にお迎えした子達。
先日ハギレで作った半襟ちゃんも大活躍です。昭和レトロな感じに仕上げました。帯揚げはそこいらにあったシルクのスカーフを代用。
ただスーパーでお買い物しに出掛けるだけですが、お着物着るだけで気分は百貨店になるんです不思議。 pic.twitter.com/ap0gJyhT9c
シルクのスカーフで代用したこちらのコーディネート。
着物や帯の色合いととてもマッチしています。
手ぬぐい
100円ショップなどでも買える手ぬぐいは、デザインも豊富です。
着物との組み合わせによって雰囲気が変わる面白さがあります。
長さが足りない場合は、2枚を縫い合わせて使うとオリジナリティが出るでしょう。
左右で色違いや違う柄にするのも、かわいくなりますね。


和風でおしゃれな柄が、カジュアルな着物によく合いそうですね。
はぎれ
お好みのはぎれも、工夫次第で帯揚げに大変身します。
古い着物のはぎれをリメイクするのもいいですね。
気温が28度近かったのでもうほぼ夏💦
— しろ (@SiRo_kmn) June 12, 2021
着物:単衣
帯:化繊の紗献上
半襟:絽
帯揚げ:アンティークのはぎれ
帯留め:骨董市でお迎えした百合
ネイルは赤に金ラメで帯留めとお揃い😊 pic.twitter.com/yG9p2HQSdT
レトロな雰囲気の着物にアンティークのはぎれが、とても良いポイントになっています。
帯揚げの役割まとめ
この記事ではまず、帯揚げの歴史と役割を紹介していきました。
- 帯揚げの登場は江戸時代末期
- お太鼓結びの帯を固定し、整えるために帯揚げが生まれた
- 明治以降はファッション小物としての意味合いが強くなっていった
帯揚げには帯の形を整えたりする機能面と、帯にアクセントを添える装飾面の二つの役割があります。
現在では枕帯を使わないときでも使用するほど、着物に欠かせないものになりました。
次に、シーン別の帯揚げの選び方を解説しました。
| シーン | 着物 | 帯揚げの選び方 |
|---|---|---|
| フォーマル (結婚式・式典など) | 留袖・訪問着・付け下げ | 白・金・銀の綸子・総絞り・紗 |
| セミフォーマル (結婚式の招待客・食事会など) | 色無地・付け下げなど | 華やかすぎない綸子・無地の縮緬 |
| カジュアル (お茶会・ショッピングなど) | 訪問着・小紋・絣(かすり) 紗や絽の夏物 | ポップな柄や鮮やかな色の縮緬・部分絞り・総柄 |
フォーマル・セミフォーマルシーンでは、格式ある上品なコーディネートを心がけます。
カジュアルな場面では、自分らしさを活かした着こなしをしましょう。
また、帯揚げの代用品として、以下を紹介しました。
- スカーフ、ストール
- 手ぬぐい
- はぎれ
これらの代用品は柄のバリエーションが多彩なので、着物を着る楽しみが広がりますね。
ちらりと見せる布ですが、このように帯揚げには深い魅力があります。
ぜひ、あなたに合った帯揚げを選んでくださいね。



ちらりと見える部分にもこだわって、TPOに合わせた着物コーディネートを楽しみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





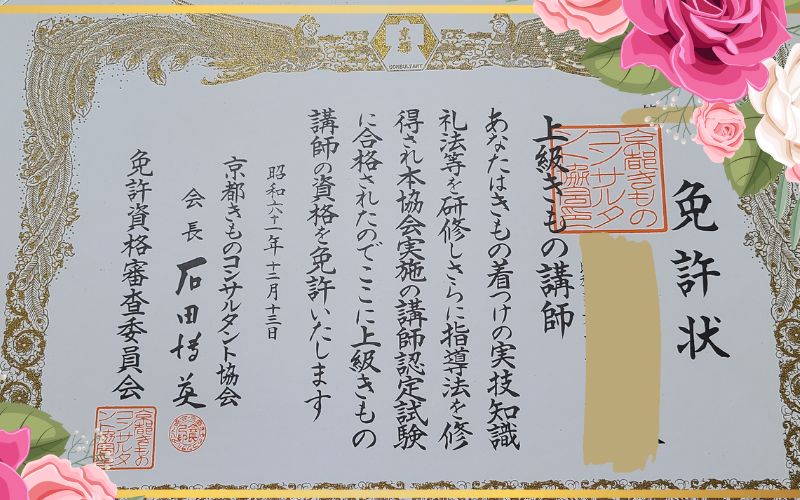

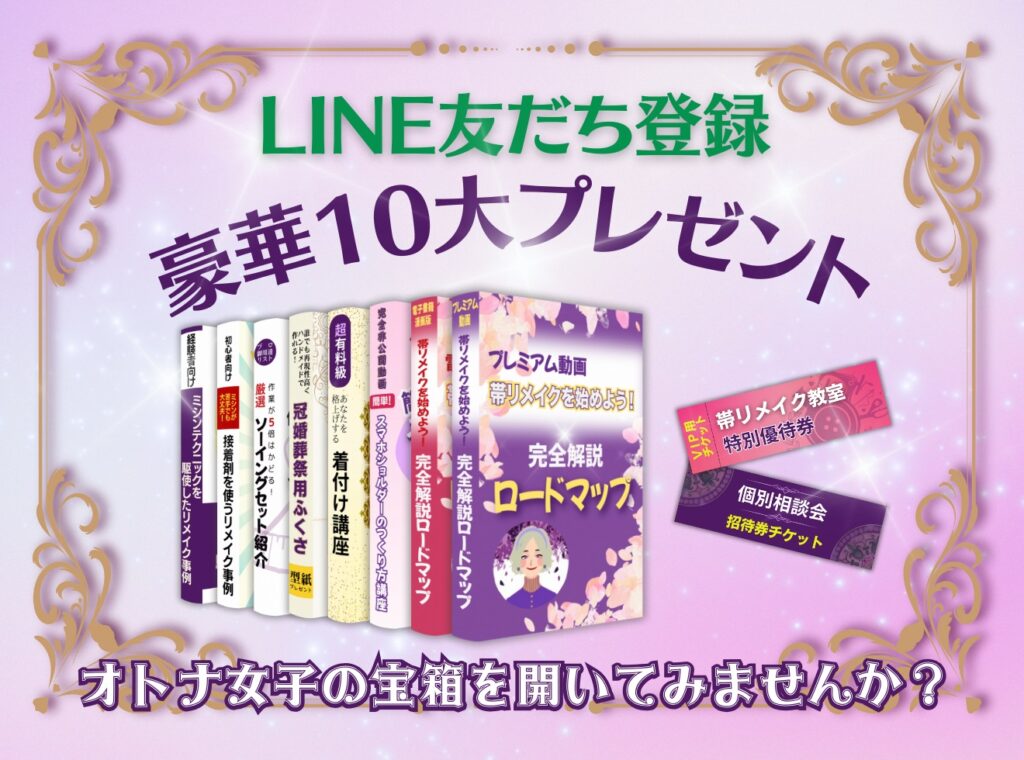
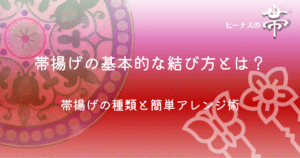
コメント