 読者様
読者様帯締めの色はどのように選んだら良いのでしょう?
「帯締めをなんとなく選んでしまい、自信がない…」
「合わせたつもりだが、なんだか浮いて見える…」
そんな経験はありませんか?
帯締めは着物や帯に比べると小さなアイテムですが、コーディネート全体の印象を左右する重要なポイントです。
帯締めが浮いて見えないようにするためには、TPOや着物の色に合わせるなどのコツを押さえることが大切ですよ。
- 帯締めの色の選び方
- 帯と帯締めの色合わせのコツ
- 帯締めの種類と格



帯締めの色の選び方や色合わせのコツがわかるので、自身を持ってコーディネートを楽しむことができますよ。
ぜひ、最後までお読みくださいね。
帯締めの色の選び方は?


帯締めとは、帯がずれたり緩んだりしないように締める紐のことであり、コーディネート全体の印象を左右する重要なアイテムです。
帯締めの色を選ぶ際には、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
- TPOに合わせて選ぶ
- 着物や帯に合わせて選ぶ
- 季節感を意識する
それぞれのポイントについて、順番に解説していきますね。
TPOに合わせて選ぶ
帯締めにも、着物と同じように格があるので、TPOに合わせて選びましょう。
いくつか選び方の例を紹介しますね。
- 留袖(第一礼装): 白を基調としたもの
- 喪服(弔事用の礼装): 黒
- その他フォーマルの場: 金銀糸を使ったもの
- カジュアルの場: 金銀糸を使用していないもの
このように、シーンに合わせた色を選ぶことが大切です。
金銀糸を使うことで華やかな印象になるので、フォーマルな場所には金銀糸が多めに組み込まれているものを使うなど、調節すると良いでしょう。
また、色使いだけでなく、帯締めの組み方によっても格式が異なるため注意が必要です。
帯締めの種類については、後ほど解説します。
着物や帯に合わせて選ぶ
帯締めだけが浮いてしまわないようにするためには、着物や帯に合わせた色を選びましょう。
着物や帯に使われている色を選べば、うまくコーディネートに馴染みやすく、上品な印象となります。
反対に、コーデにアクセントをつけたい場合は、着物や帯の色とは反対の補色を選ぶことで、引き締まった印象を与えることができますよ。


たとえば、赤系の着物に補色である緑の帯締めを使うことで、アクセントや引き締め効果を期待できます。
同系色を選ぶか、補色を選ぶかで印象は異なるので、その時々に合う帯締めを選んでみましょう。
季節感を意識する
うまく着こなすためには、季節に合わせて帯締めの色を選ぶことも大切です。
- 春:桜色・若草色・藤色など、明るくて淡い色味
- 夏:白色・水色など、涼しげな色
- 秋:オレンジ・からし色・えんじ色など、深みのある色
- 冬:赤色・紺色など、深みのある色
春は桜色や若草色・藤色など、爽やかで温かみのあるな色を選ぶと良いでしょう。
こちらは夏らしい透け感のある帯締めです。
白地のレース素材なので、涼しげな印象を与えられますよ。
秋から冬にかけては、深みのある色を合わせるのがおすすめです。
明るい色の着物にも深みのある色を合わせることで、落ち着いた印象となり、冬らしいコーデになりますよ。
また、素材によっても印象が異なるので、季節に会ったものを選ぶと良いでしょう。
たとえば、夏は透け感のある素材だと、さらに涼しげな印象を与えることができます。
冬は年末年始などでフォーマルなシーンも多いので、光沢感がある素材だとより華やかで映えます。
このように季節ごとに合った帯締めを選ぶことで、同じ着物でも違った雰囲気で楽しむことができますよ。
帯と帯締めの色合わせのコツ





着物や帯に合わせて帯締めを選んだつもりが、合わせてみるとなんだか思っていたのと違う…



なんだかしっくりこない場合は、色味が合っていないのかもしれませんね。
そこでこちらの章では、帯と帯締めの色合わせのコツを紹介します。
- 色のトーンを合わせる
- 実際に帯や着物に合わせて選ぶ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
色のトーンを合わせる
帯締め選びでは、色そのものだけでなくトーンを合わせることも重要なポイントです。
帯締めがなんとなくしっくりこないと感じるときは、着物や帯のトーンと合っていないのかもしれません。
たとえば、赤色と一口に言っても、明るさや鮮やかさはさまざまです。
着物や帯と明るさが異なる赤色を持ってくると、帯締めだけが浮いて見えてしまうこともあるので、注意が必要です。
実際に着物や帯に合わせて選ぶ
確実に色を合わせたい場合は、実際に着物や帯と合わせながら選ぶのがおすすめです。
複数の色が使われている帯締めの場合、実際に来てみることで帯締めの見える位置や範囲が変わり、見た目の印象が異なることがあります。
また、色のトーンが異なる場合も、実際に合わせてみることで気づきやすくなりますよ。
とはいえ、着物を持ち運ぶのは難しいこともあるでしょう。
できる範囲で帯だけ持参したり、色味がわかる写真を残しておいたりすると、スムーズですよ。
帯締めの種類と格を知って正しく装おう


帯締めには大きく分けて組紐と丸くげの2種類があり、一般的に組紐のほうが格式が高いとされています。
組紐:複数の糸を組み合わせて作られた糸
丸くげ:布を筒状にして、その中に綿を入れて作った紐
着物や帯と同じように、TPOに合わせて選ぶと良いでしょう。
平組(平打ち)
平組はその名の通り平たく組まれているのがが特徴で、組紐の中でも最も高い格式です。


一般的に幅が広い平組はフォーマルの場面で使われることが多く、狭いものはカジュアルシーンで使われることが多くなります。
特に幅が16mm以上の平組は、結婚式などの第一礼装にも用いられます。
幅が狭めの「三分紐(さんぶひも)」や、組目が細かく重厚な質感が特徴の「高麗組(こうらいぐみ)」などがあります。
帯留目を使う場合には、細めの三分紐がおすすめですよ
丸組(丸打ち)
平組の次に格式が高いのが丸組で、飾りがついた訪問着などの準礼装でも使われる帯締めです。


見た目は立体的で柔らかいので、いろいろな結び方ができます。
表裏がなく結びやすいため、着付けに慣れていない初心者の方にもおすすめですよ。
角組(角打ち)
角紐は紐の断面が正方形になるように組まれている紐です。


小紋や木綿などの普段着に用いられることが多いです。
角組は厚みがあるため、他の紐よりも結びにくいと感じることが多いようです。
ただし、角組のうちの1つである「冠組」は、伸縮性があるため伸びやすく、訪問着などのフォーマルシーンからカジュアルシーンまで幅広く使われています。
丸くげ
丸くげは複数の糸を組んで作る組紐と違い、筒状状にした布の中に綿を入れて作ります。


準礼装などに使われることも稀にあるようですが、一般的に大人のフォーマルシーンで使われることはほとんどありません。
普段着や子どもの着物など、カジュアルシーンで使われることが多いです。
フォーマルシーンで使う場合は、平組などしっかりした印象の組紐がおすすめですよ。
レース組
近年、夏向けの帯締めとしてレース組みが人気です。
透け感があるので、涼しげな印象を与えることができますよ。
金糸や銀糸が使われているタイプもあり、華やかさをプラスすることも可能です。
ただし、格式の高い着物にはあまりふさわしくないため、使用は控えた方が良いでしょう。
帯締めの色の選び方 まとめ
この記事では帯締めの選び方について解説してきました。
帯締めの色を選ぶ際には、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
- TPOに合わせる
- 着物や帯に合わせる
- 季節感を意識する
可能であれば、着物や帯と実際に合わせながら選ぶと、ぴったりの帯締めを見つけやすくなりますよ。
帯と帯締めの色合わせのコツは以下のとおりです。
- 色のトーンを合わせる
- 実際に帯や着物に合わせて選ぶ
たとえば、帯だけをお持ちいただくか、色味のわかる写真を残しておくと、コーディネートがぐっとスムーズになりますね。
帯締めの種類と格を知って装うために必要なことは以下のとおりです。
組紐:複数の糸を組み合わせて作られた糸
丸くげ:布を筒状にして、その中に綿を入れて作った紐
帯締めには大きく分けて組紐と丸くげの2種類があり、一般的に組紐のほうが格式が高いとされています。
- 平組(平打ち):平たく組まれているのがが特徴で、組紐の中でも最も高い格式。
- 丸組(丸打ち):平組の次に格式が高く、飾りがついた訪問着などの準礼装でも使われる。
- 角組(角打ち):角組の一種「冠組」は、伸縮性があり、フォーマルからカジュアルまで幅広く使える。
- 丸くげ:普段着や子どもの着物など、カジュアルシーンで使われることが多い
- レース組:金糸や銀糸が使われているタイプもあり、華やかさをプラスすることも可能
帯締めの色選びは、全体のコーディネートを引き立てる大切なポイントです。
着物や帯の色柄とのバランスを考えながら、差し色としてアクセントを加えたり、同系色で上品にまとめたりと、シーンや季節に合わせて楽しみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



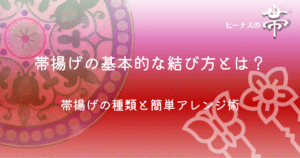

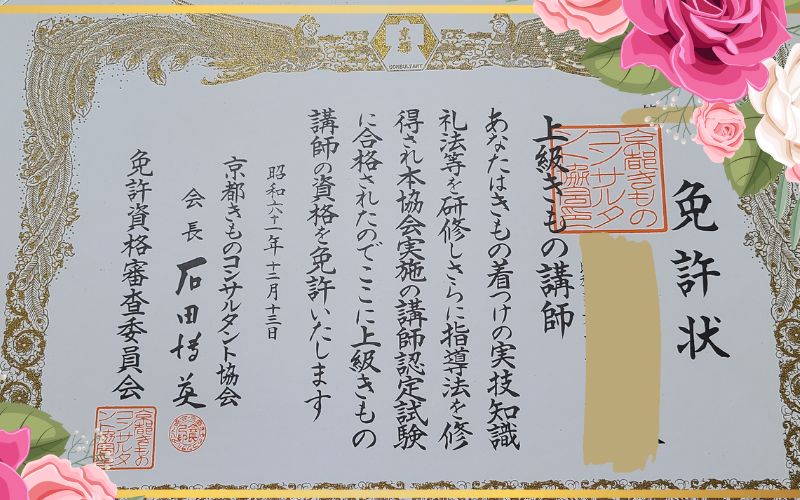

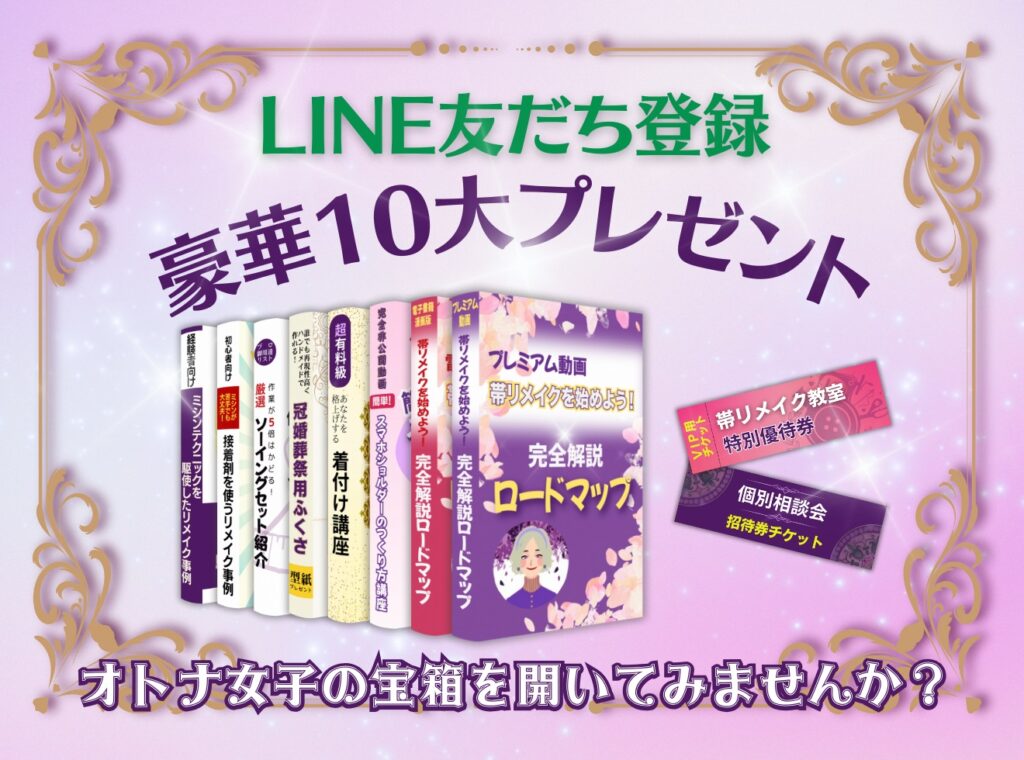

コメント