 読者さま
読者さま以前からよく目にしているこの柄は青海波という名前なんですね。



はい。そうです。
青海波は古くから人々に愛されている文様ですね。
穏やかな波がいつまでも続いていく文様「青海波(せいがいは)」。
「青海波」を眺めていると静かで大きな海を感じて、心が落ち着いてくるような気がします。
海の波ではなく電波ですが、wifiのマークが「青海波」に似ていると話題になったこともあるようです。
・「青海波」と呼ばれる由来
・私たちの周りにある「青海波」
・帯、着物で使われている「青海波」のデザイン
この記事では、「青海波」の模様の意味や歴史、魅力についてわかりやすくご紹介します。
ぜひ、最後までお読みください。
帯の柄「青海波」とは?人気の伝統文様の意味を知ろう
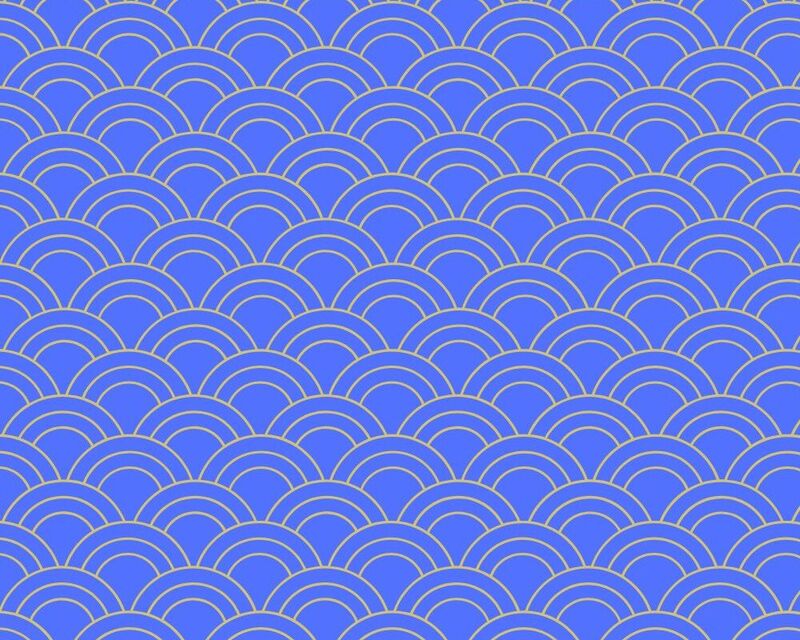
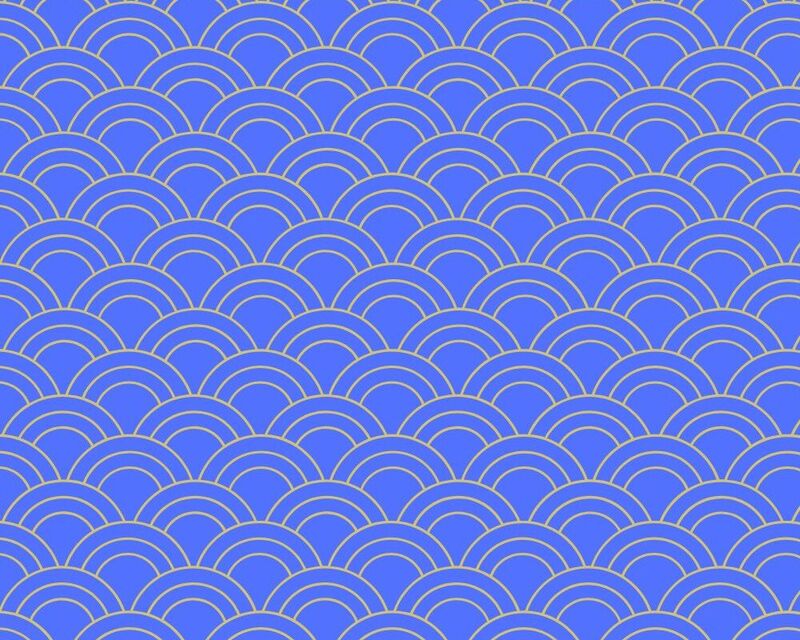
「青海波」を帯の柄などで目にすることがありますね。
縁起が良いと言われていますが、どんな意味を持っているのでしょうか。
「青海波」があらわす縁起の良い意味
「青海波」は、静かに穏やかに、波がいつまでも続いていく文様です。
その様子から、昔の人々は「青海波」に「未来永劫平和な生活が続く」という願いを込めたのでしょう。
「青海波」のデザインは、その縁起の良さから結婚式や誕生日などの様々なお祝いに使用されている吉祥文様です。
それぞれの文様が持つ意味
古来から続くたくさんの文様が「青海波」の他にもあり、それぞれ縁起の良い意味があります。
一部をご紹介しますね。
| 文様の名前 | 文様の持つ意味 |
| 観世水 | 清らかさ、魔除け、火除け |
| 雪輪 | 豊作の象徴 |
| 七宝 | 円満、調和 |
| 籠目 | 魔除け |
| 桜 | 豊かさ、繁栄 |
| 菊 | 不老不死、延命長寿、無病息災 |



ひとつひとつの文様にこめられているたくさんの思いは、現代の私たちが持つ願いでもありますね。
観世水について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。


帯の柄「青海波」はどこから来たの?伝統的な文様の歴史


私たちのまわりで、よく目にしている「青海波」。
和を感じさせる「青海波」ですが、そのルーツは意外にも海外です。
「青海波」の成り立ち
和風なデザインという認識を持っている方が多数派と思われる「青海波」。
しかし、意外にも日本生まれではありません。
古代ペルシャからシルクロードを通って飛鳥時代に日本に伝わりました。
平安時代になると、雅楽に由来してこの名で呼ばれるようになります。
その後、江戸時代中期に塗師によって広まりました。
雅楽の「青海波」と、源氏物語の中の「青海波」
文様「青海波」は飛鳥時代に伝わりました。
平安時代になると雅楽の「青海波」の装束にこの文様が使用されます。
それが由来となり、「青海波」という名称で呼ばれるようになりました。
雅楽「青海波」は婆羅門僧正が天竺(てんじく)にて聞いて伝えたといわれています。
出典元:zenya250
また、源氏物語では第七帖「紅葉賀」で雅楽の「青海波」が登場します。
秋の夕暮れ、色づく紅葉の下で光源氏が頭中将と二人で「青海波」を舞う場面です。
雅楽を見ながら、文学の中の「青海波」を想像してみるのも楽しいですね。
「青海波」を舞う光源氏と頭中将は、夕暮れ、紅葉の色と相まって、幻想的に美しかったのではないでしょうか。
実はこんなところにも!「青海波」のデザインは身近に見つかるかも?


江戸時代に、塗師(ぬし)である青海勘七が特殊な刷毛で「青海波」を描きました。
その巧みな技術、青海波塗りから人気が広まったとされています。
ぬり‐し【塗(り)師】
読み方:ぬりし漆細工や漆器の製造に従事する職人。
引用:weblio辞書
皿や湯呑などの食器、雑貨のデザイン
「青海波」のデザインは日常的に使われています。
今までは気が付かなかったところで、ふと「青海波」を発見することもあるかもしれません。
「紗綾型(さやがた)」や「矢絣(やがすり)」などとともにラグビーワールドカップのユニフォームに使われたこともあります。
工芸や手芸、建築にも!親しまれる青海波
工芸や手芸、また建物などでも「青海波」が活躍しています。
家の中や町を見回すと、どこかの風景に「青海波」がひっそりと馴染んでいますよ。
昔も今も愛される「青海波」受け継がれる文様と現代デザイン


波をあらわしている「青海波」は夏の涼しげな装いとして使われることも多く、浴衣や手ぬぐい、うちわなどにもよく見られるデザインです。
また、吉祥文様としての意味をもつ「青海波」はお祝い事や通年でも使用できます。
しかし、「青海波」に他の文様を組み合わせると、その文様があらわす季節にふさわしいものに変化します。
「青海波」はいくつもの魅力をもっていますね。
フォーマルな場面よりも、普段のおしゃれや街歩きにちょうどいいカジュアルな格の帯です。
「青海波」の帯や着物
「青海波」が主役になったデザイン、着物の地が全体的に「青海波」になっているデザイン、奇抜な色使いなどがあります。
青海波が途切れていたり、ところどころに散らしてあるものは「破れ青海波」と言います。
「青海波」と他の文様の組み合わせをデザインした帯や着物
「青海波」の波が他の文様になっていたり、色違いにしたりと、そのデザインは無限に存在します。
これは!というお気に入りのデザインに出会えるかもしれません。
帯の柄「青海波」~いくつもの時代を超えて続く穏やかな波~
今回は、帯の柄「青海波」について解説しました。
吉祥文様である「青海波」は穏やかな波がいつまでも続く様子から「未来永劫平和な生活が続く」という願いが込められています。
・「青海波」は古代ペルシャからシルクロードを経て飛鳥時代に日本に伝わった。
・雅楽「青海波」の装束に使われたことからこの名前で呼ばれるようになった。
雅楽「青海波」は源氏物語にも登場した。
・江戸時代中期に塗師の青海勘七の巧みな技法により広く知られる文様となった。
「青海波」は、飛鳥時代に日本に伝わり、平安時代にその名称で呼ばれるようになり、江戸時代に広まりました。
現代ではwifiのマークが似ていると話題になるなど、波が何度も寄せるようにムーブを繰り返しているようです。
次はいつの時代にどんな広がりを見せてくれるのか期待してしまいますね。
波が涼しげなイメージの「青海波」は、夏物、浴衣、雑貨の柄などに使われています。
一方で、帯や着物の柄としては、吉祥文様として通年で使える柄であるため広く長く親しまれています。
特にちょっとしたお出かけや、おしゃれ着物に合わせるのにちょうどいい、カジュアル寄りの帯です。
「青海波」と様々な文様との組み合わせを、見た目の美しさと意味の深さ、どちらも楽しみながらより一層の華やかさと幸せへの思いを身にまとってみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
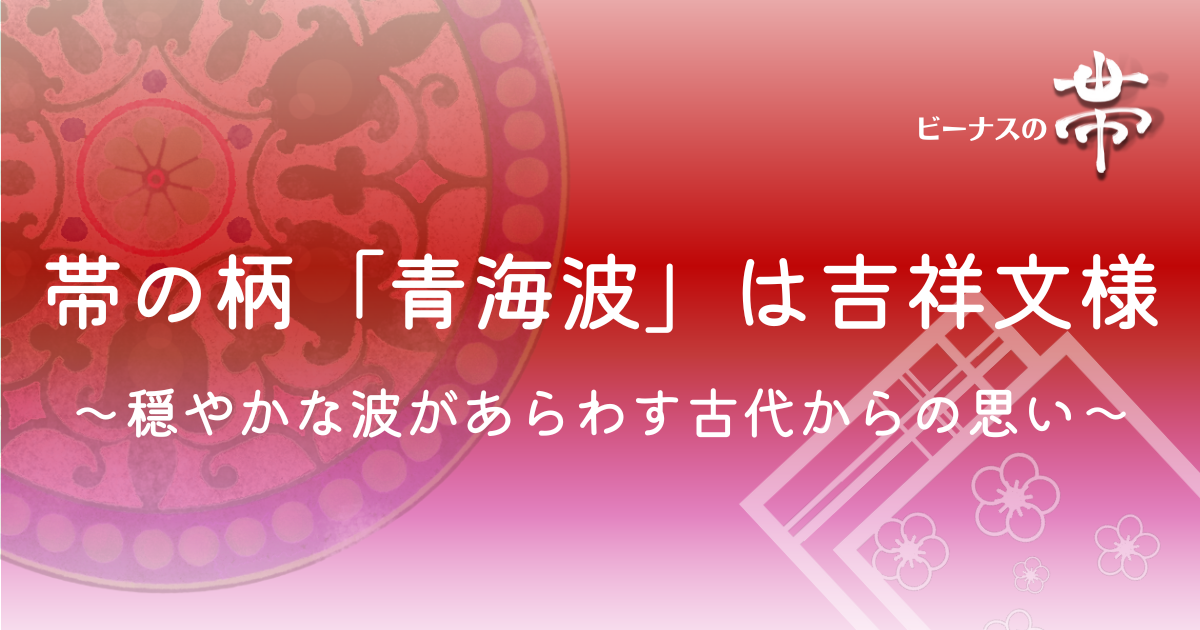
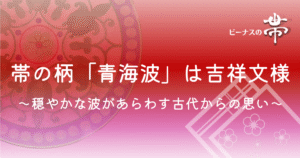
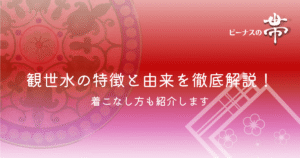


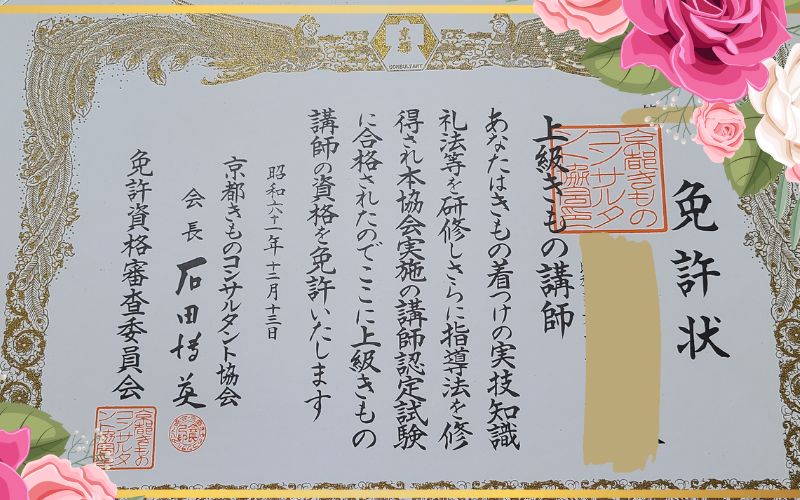

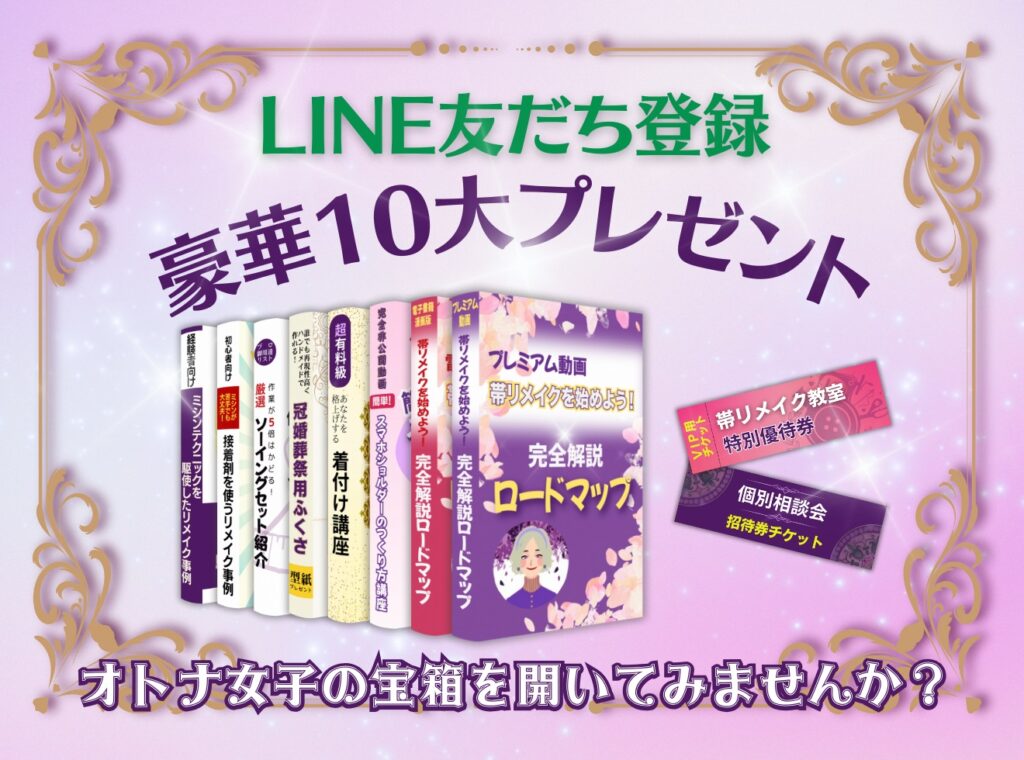
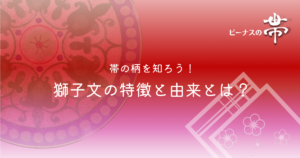


コメント