 読者さま
読者さま獅子文っていう帯の模様があるらしいけれど、どんな模様なの?
なんで獅子が帯のモチーフになっているの?
獅子文(ししもん)とはその名のとおり、獅子を模様として織り込んだ柄のことです。
牡丹と唐獅子を組み合わせた唐獅子牡丹(からじしぼたん)や、獅子舞でおなじみの毛卍文(けまんじもん)など、さまざまな種類があります。
その由来は古く、なんと奈良時代からの伝統ある模様です。
この記事では、獅子文の由来や種類のほか、獅子文が織り込まれた帯を利用する季節について解説します。



そのほかにも、獅子文様の帯地を使ったリメイク品も紹介しますね!
- 獅子文の由来
- 4種類の獅子文
- 獅子文を使ったコーディネートとリメイク
格式高い獅子文の魅力を知れば、その歴史を身にまとってみたくなること間違いなしですよ。
ぜひ、最後までお読みくださいね。
獅子文とはどんな模様?


奈良時代から現在まで続く獅子文の起源は、3〜7世紀のササン朝ペルシアにあります。
この章では、架空の動物である獅子が生まれた背景や、獅子文の由来について解説していきます。
架空の動物・獅子とは
獅子文のモデルとなった獅子とは、ライオンをもとに生まれた架空の動物です。
古代のライオンはアフリカとインドだけでなく、中近東や西アジア、ヨーロッパ南部にも生息していました。
古来からライオンは王権や太陽の象徴であったため、野生のライオンが生息していない国でも文様として利用されていたのです。
日本には仏教とともにシルクロードを経て中国から伝わったため、「唐獅子」と呼ぶこともあります。
獅子の特徴は以下のとおりです。
- 悪霊を退散させる力がある
- 知恵を司る仏である文殊菩薩の乗り物
- 獅子舞や狛犬、シーサーと同じく中国経由で伝わったライオンがモチーフ
- 巻き毛のたてがみと体毛を持つ
獅子のモデルはライオンですが、本物よりエキゾチックで宗教的な雰囲気であることがわかりますね。
獅子文の由来はなに?
獅子文のルーツはシルクロードを渡って伝わった、西アジアの伝統的図像にあります。
獅子文は西アジアから中国を通じて日本に入り、正倉院に宝物として保管されました。
そのため、正倉院文様の一種に分類されています。
正倉院には、「正倉院裂(しょうそういんぎれ)」と呼ばれた織物も多くあります。
獅子文をはじめとする「正倉院文様」は格の高い文様。
おもに留袖や訪問着、袋帯など、お祝いのシーンに活用されています。



古代ペルシア生まれの獅子文は、エキゾチックかつ重厚な雰囲気を持っています。獅子は縁起の良い動物なので、お祝いの場にはぴったりですね。
獅子文は帯や着物だけでなく、刀や鎧といった武具、馬具など幅広い用途に使われていました。
獅子を織り込んだ4種類の文様


ここでは、獅子の姿を織り込んだ4種類の文様について紹介していきます。
どの文様も獅子をモチーフとしている点は共通していますが、それぞれに違った意味が込められているのです。
獅子狩文様(ししかりもんよう)
獅子狩文様は狩猟文(しゅりょうもん)の一種で、馬に乗った武者が弓で獅子を射る様子を表現した文様です。
この生地では円の中の赤い模様が獅子を表していますが、狩猟文には獅子だけでなく、ウサギ・鹿・イノシシ・羊などの模様もあります。
ササン朝ペルシアで流行した動物闘争文様がアレンジされて獅子狩文様が生み出され、シルクロードを経由して日本に伝わりました。
唐獅子牡丹(からじしぼたん)
唐獅子牡丹は、百獣の王・獅子と中国の唐代に百花の王・牡丹を組み合わせた模様です。
文殊菩薩の使いである獅子は、牡丹の花からしたたる露を口にすることで、たてがみに寄生する虫から身を守ると言われています。
この伝説から獅子と牡丹はお約束の組み合わせとされ、帯や着物の柄でも一緒に取り入れられるようになりました。
「牡丹に唐獅子」という取り合わせのよいものを表す言葉もあるように、唐獅子と牡丹は切っても切り離せない関係なのです。
獅噛文(しがみもん)
獅噛文は牙をむいた獅子の顔を、横一直線に並べた魔除けの文様です。
獅子の恐ろしい顔を模様にしたものを身にまとうことで、「悪いものを寄せつけない」という意味があります。
力強い色使いと異国情緒を感じさせるこちらの模様が、大きく口を開けた獅子の顔をモチーフとする獅噛文です。
獅噛文のルーツは中国の殷・周時代に青銅器の装飾として用いられた饕餮文(とうてつもん)と言われています。
饕餮は財産や食物をむさぼる、中国神話の怪物のこと。
なんでも食べるという設定が転じて、魔を食べる、つまり魔除けの意味を持つようになりました。
毛卍文(けまんもん)
毛卍文は獅子そのものではなく、「卍(まんじ)」のように渦巻いた体毛を表した文様です。
太陽の力を表しており、獅子舞のかぶる布の模様としても知られています。
毛卍文は、図案化した太陽によく似ていますね。



獅子舞の胴体だから体毛を表す毛卍文を使っていたなんて、知りませんでした。獅子舞の風呂敷は唐草模様じゃなかったんですね!
獅子の体毛の模様なので「獅子毛」の別名で呼ばれることもあります。
獅子文を着てもいい季節っていつ?


帯や着物には、季節によってふさわしい柄があります。
たとえば、桜模様の帯を冬に使ったり、紅葉柄の帯を秋に使うと違和感を覚えてしまいますよね。
そこでここでは、獅子文を着るベストシーズンや獅子文を使ったコーディネートを、詳しく解説していきます。
獅子文はどの季節に着ても大丈夫!
獅子文には季節による制限はないので、いつ着ても問題ありません。
しかし、植物と組み合わせた文様の場合は、その植物が盛りを迎える季節に着るのがベストです。
季節ごとにふさわしい植物を知っておきましょう。
| 春 | 桜、牡丹、杜若(かきつばた)、藤、菖蒲(あやめ) |
| 夏 | 紫陽花、撫子、朝顔、竹 |
| 秋 | 萩、桔梗、紅葉、菊、葡萄 |
| 冬 | 松、椿、梅、南天 |
お約束の組み合わせである唐獅子牡丹は、牡丹が春の花なので4月〜5月に着るのがおすすめ。
ただし唐獅子牡丹は吉祥模様の1つなので、あまり写実的な柄でなければ、春以外に着ても問題ありません。
季節ごとの柄に厳格な規則はありませんが、おしゃれな着こなしをめざすのなら、季節感はぜひおさえておきたいポイントですね。
獅子文を使った着こなしとリメイク品


この章では、獅子文を使ったコーディネート例と、獅子文の帯や着物をリメイクした作品をSNSから引用していきます。
どれも素敵なものばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
獅子文を使ったコーディネート
獅子文は吉祥文様のひとつですが、結婚式やパーティー以外のお出かけに着用しても問題ありません。
エキゾチックな着物を着たい時や、周りの人と柄をかぶらせたくない時に、獅子文はピッタリな文様ですよ。
大人っぽい赤色にターコイズの花器の模様が映える着物に、黄色を基調とした獅子文の名古屋帯を組み合わせた和装。
背面から見ると獅子の姿が目立っていて、インパクト抜群ですね。
白地に濃い緑と紫色の牡丹柄の着物に、これまた紫色の獅子文の帯が毒々しくも目を引く組み合わせ。
牡丹と獅子はどちらもおめでたい柄であり、着物の文様では定番です。
伝統的で重々しいイメージのある獅子文ですが、コーディネート次第ではがらりとイメージが変わります。
獅子文を使ったリメイク品
手もとにある帯が汚れたり破れていたりしていると、帯として使うのはためらいますよね。
その場合は、リメイクしてバッグや帽子に生まれ変わらせましょう。
2枚目の画像が獅子文のガウンです。
ゆるやかなシルエットのガウンは、獅子文によって落ち着いた風格をかもし出しています。
男性向けの着物ガウンのようですが、女性が着ても渋くてかっこいいですね。
唐獅子牡丹の帯を帽子に仕立て直したリメイク品。
右側は牡丹、左側は唐獅子とモチーフが異なるので、見る角度によって印象が変わります。
男性でもかぶりやすいのも、獅子文の魅力のひとつですね。
威厳ある獅子をメインにしたトートバッグと、がま口財布型のショルダーバッグ。
全体的に色合いが渋くてかっこよく、年を重ねても長く使えそうですね。
縁起のいい獅子文をかっこよく着こなそう
獅子文は帯の柄の中では格が高い文様で、訪問着や袋帯に使われることが多く、おもにパーティーや祝い事の席で着用します。
獅子という、ライオンとは似て非なる動物が描かれているのが最大の特徴です。
- モデルはライオン
- 日本や中国にはライオンが生息しなかったため、かなりの部分がライオンと異なる
- 悪霊をはらう力を持つ
獅子文は3〜7世紀のササン朝ペルシアにルーツを持ち、日本では奈良時代から用いられるようになりました。
獅子を使った文様には、主に以下の4種類があります。
- 獅子狩文様
- 唐獅子牡丹
- 獅噛文
- 毛卍文
それぞれ獅子の姿や体の一部分を表したおめでたい文様なので、一年を通して着用できます。
ただし、季節感のある植物と一緒のモチーフになっている場合は、植物の季節に合わせて着用しましょう。
エキゾチックな魅力と1000年以上の伝統を持つ獅子文は、組み合わせ次第では日常のお出かけにも使える文様です。
ぜひ、獅子文を普段の生活に取り入れて、着物を楽しんでみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
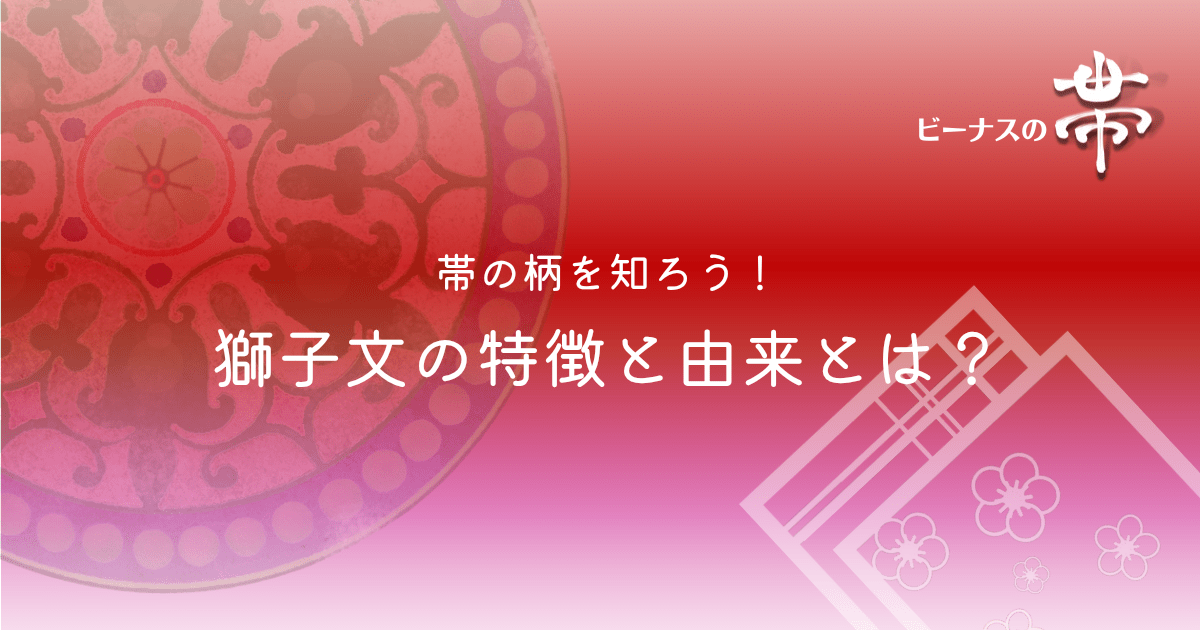
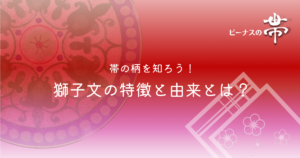

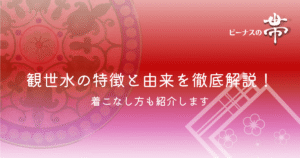

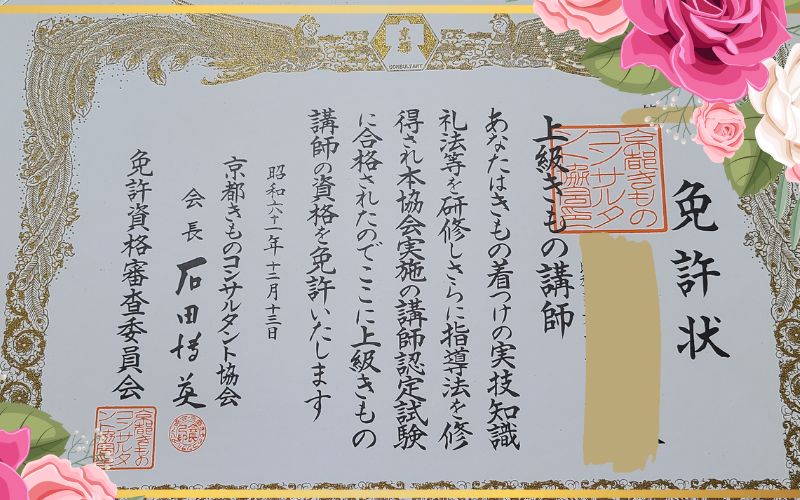

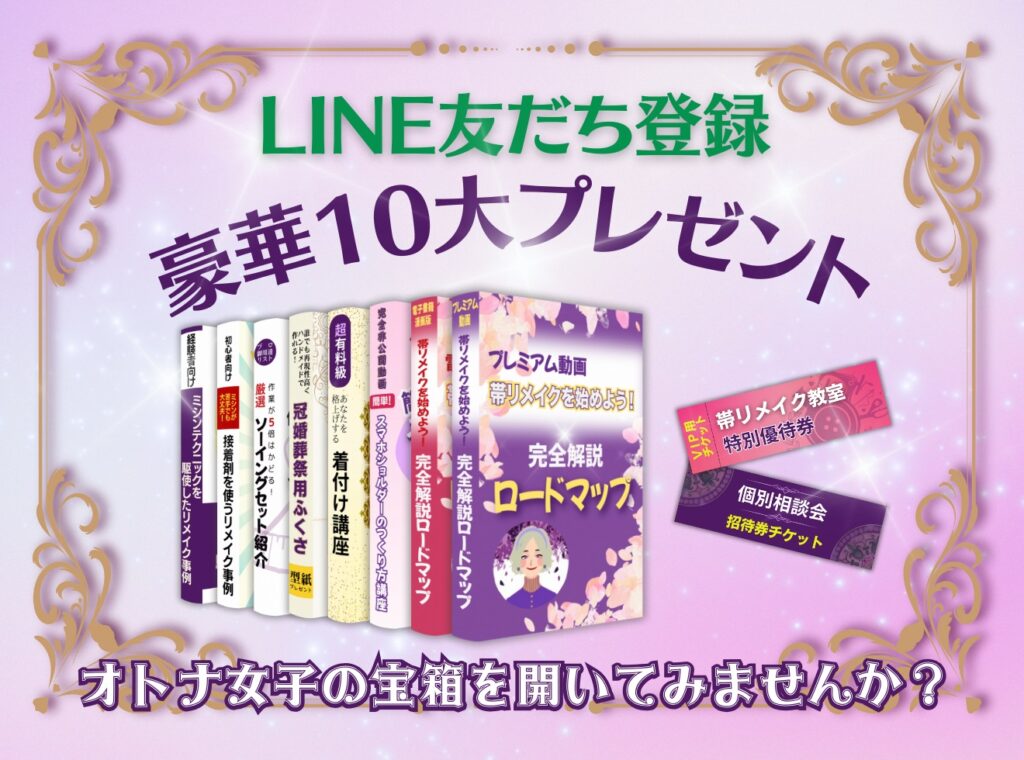

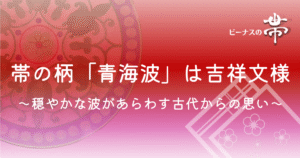

コメント