 読者さま
読者さま訪問着を着ようと久しぶりにタンスを開けてビックリ。帯からなんだかカビ臭いニオイがしました・・・・・・。



着物や帯はずっとタンスにしまったままなので、今さら開けるのが怖いです。
日本では日常的に着物を着る時代もありましたが、最近はすっかりその機会は減ってしまいました。
身内の結婚式でもご両親以外なら洋装で出席する方も多いのではないでしょうか。
長い間タンスの中で眠っている帯。
お嫁にいくときにあつらえたり、母親や祖母から譲ってもらったりしたものもあるでしょう。
そんな思いの詰まった大切な帯にカビが生えるのは悲しいですよね。
帯がこれ以上傷まないように、新たなシミやカビを発生させないように保管する方法がわかれば嬉しいですね。
この記事では、帯のお手入れ方法やカビが生えてしまった時の対処法と予防法について解説していきます。
- 帯にカビが生える理由
- 帯にカビを見つけたときの対処法
- 帯にカビを生やさないためのお手入れ方法



帯のカビは、程度によっては自宅で対処できる場合もありますよ! 正しく保管して次の世代に受け継ぎたいですね。
ぜひ、読みすすめてくださいね。
帯にカビが生える理由を知りましょう


非常にデリケートな帯ですが、正しく保管すれば何十年と着用することができます。
ですが、ただタンスの中に大切にしまっておくだけでは帯をカビから守ることは難しいでしょう。
ここでは、帯のカビについて以下の順で解説します。
- カビが生える原因
- カビの種類の見分け方
- 帯でカビが生えやすいところ
カビが生える原因
そもそもカビが生える原因は以下の4つの条件がそろうときです。
- 60%以上の湿度
- 5~35℃の温度
- 酸素
- タンパク質
帯に生えるカビを防ぐにはこの4つの条件をできるだけ避けなければなりません。
しかし、私たちが暮らす日本の高温多湿な気候は、カビが生える条件をしっかり満たしています。
そして、カビのエサになるのがタンパク質。
帯に使われることが多い絹は約70%がタンパク質です。
さらに着用後の帯に残りがちな食べ物のカス、人間の髪の毛や皮膚もタンパク質です。
これを知ると、カビが好む条件がそろう日本で帯を保管することがどれだけ難しいことかよく分かりますよね。



まさにカビとの戦いですね。
カビの種類の見分け方
カビと一口に言っても進行度合いで種類が分かれます。
カビは発生してから時間が経つにつれ「白」→「黄」→「黒(こげ茶)」と色が変化します。
時間の経過とともに根深くなり、除去する難易度も上がると考えてください。
斑点状の白いカビで発生して間もないカビ。
帯の表面に現れる。
応急処置で除去できる可能性がある。
白カビを数年間放置すると黄カビに。
白カビより根深いため素人での除去は難しい。
クリーニングが必要。
白カビ発生から10年以上経ったカビ。
クリーニングでも修復は困難。
黒カビに変化する前の対策が必須。



カビの色を観察すれば、どのくらい進行しているかがわかるのね。
帯でカビが生えやすいところ
そもそも帯のどこにカビが生えるのでしょうか?
帯芯
帯で1番カビが生えやすいのは帯芯です。



帯芯とは帯の内側に縫い付けられている布地のこと。
硬さと厚みを調節し、帯の形をきれいに保つ役割があります。
- 帯芯には絹が使われていることが多い
- 帯の一巻き目や帯枕を当てる場所は汗がしみこみやすく湿気がこもりやすい
カビの好物であるタンパク質と湿気のダブルコンボでカビが生えやすくなります。
帯芯は帯の内側にあるため見た目では判断しづらく、タンスを開けたときのプンとしたカビ臭でわかることが多いです。
表地や裏地
「帯の表地や裏地にカビがある=帯芯にできたカビが広がってきた」と考えてほぼ間違いありません。
残念ながら帯の表面に目視できるカビがある場合、進行したカビ(黄カビ・黒カビ)の段階であることがほとんどです。



帯に生えるカビは目に見えない帯芯部分から始まるからわかりにくいのね。



気付いたときには進行してるなんて・・・・・・。
一体どうしたらいいのかしら。
では、つぎは帯のカビに気が付いたときの対処法をお伝えします。
帯にカビを発見したらどうしたらいい?


久しぶりにタンスから出した帯にカビを発見したときの対処法をお伝えします。
初期のカビに自宅でできる応急処置
幸運にもカビを早く発見できた場合は、応急処置としてすぐに試してほしい方法があります。
それは帯を風に当てて湿気を飛ばすことです。
屋内でも屋外でも構いませんが、直射日光を避け4~5時間ほど干すのを1ヶ月ほど繰り返しましょう。
屋外で干す場合は夜間は厳禁、屋内では窓を開けて換気しながら行うのがおすすめです。
扇風機の風やドライヤーの冷風を当てるのも1つの手ですよ。



注意!マスクをしてカビ菌を吸い込むのを防ぎましょう。
帯のカビにやってはいけない対処法
帯に生えたカビを見つけたとき、思わずしてしまいがちなNG行動をご紹介します。
- 消臭スプレーをする
- アルコールで拭く
- アイロンをかける
- 濡れタオルで拭く



洋服と同じ感覚で対処してしまいそうになりますが、これらはすべて帯を傷めてしまう行動です。
× 消臭スプレーをする
1ヶ月も繰り返し干すなんて面倒!という気持ちはわかりますが、市販の消臭スプレーを使うのはやめましょう。
消臭スプレーはベースが水なので輪ジミ、水シミなどの取れないシミができてしまいます。
× アルコールで拭く
殺菌力が強いアルコールはフキンや衣類のカビ取りには使えますが、洗えない帯には厳禁です。
染料や繊維によっては変色や色抜け、色あせが起きてしまいます。
× アイロンをかける
動物やタバコの臭いに効果的なスチームアイロンですが、カビには効果がありません。
それどころか、帯の生地が縮んで元に戻らなくなる可能性がありますよ。
蒸気を当てることにより湿気を含みカビが増殖することも考えられます。
× 濡れタオルで拭く
フワフワした白カビを発見したら、とっさに濡れタオルで拭ってしまいたくなるかもしれません。
しかし擦ることで帯の生地を傷めたり、濡れタオルの水分でさらにカビが増えたりする危険性があります。
カビ臭さが消えない場合は着物専門のクリーニング店に依頼
カビの発生頻度が高い帯芯。
応急処置をしてもカビ臭が消えない場合は、帯芯のカビの程度も進んでいると考えられます。
そんなときは帯芯を交換するのがおすすめですよ。
帯芯の交換は一度帯をほどいて布の状態に戻し、帯芯を取り替える作業です。
個人では難しいので、潔く着物専門のクリーニング店にお願いしましょう。



クリーニング店を選ぶときは帯をほどいて洗う「洗い張り」のメニューがあるかどうかを確認するといいですよ。
こちらの記事は、着物帯専門のクリーニング店についてご紹介しています。
あわせてお読みください。
カビを生やさないための予防法を学びましょう


帯をよい状態で保管していくためにはカビを寄せ付けない環境づくりに力を入れましょう。
帯のカビを予防するポイントは5つあります。
- 着用後は陰干しする
- たとう紙に包んで保管する
- 除湿剤を使う
- 定期的に虫干しする
- 着用する機会を作る
着用後はすぐに陰干し
着用した帯には汗がしみこみ、さらには空気中の湿気がこもりがちです。
そのままタンスにしまうと、湿気大好きなカビのえじきになってしまいます。
ブラシで軽くホコリを落とした後は、必ず風通しのよい室内で陰干しをしましょう。
直射日光を避けて半日程度行うとよいですよ。



特にたくさん汗をかいたときは専門のクリーニング店で汗抜きの処理をしてもらうのがおすすめです。
保管はたとう紙で
帯の保管は必ずたとう紙で包みましょう。



たとう紙とは着物や帯を包む専用の包み紙のこと。着物に湿気が付かないように空気中の湿気も吸ってくれます。
カビは湿気が大好物。
帯のカビ予防に、たとう紙はなくてはならないアイテムです。
ただし、たとう紙が湿気でふにゃふにゃになったり黄ばんだりしてくると劣化のサインとなります。
見た目に変化がなくても3年程度で交換するようにしましょう。
除湿剤を使う
タンスの中の湿気を防ぐために除湿剤を活用しましょう。
変色の原因になるので帯に直接触れないところに置くのがポイントです。
さらに部屋の湿気対策も効果があります。
湿気の高い梅雨時は除湿器を使うのもおすすめですよ。
定期的な虫干し
帯はタンスに入れたままだと湿気を含みやすく、虫が付くことも・・・・・・。
年に2~3回、帯を広げて湿気をとばす虫干しを行うとカビ対策になります。
直射日光の当たらない室内で換気をしながら、ハンガーに掛けて干しましょう。
時間は午前中~午後3時くらいがベストです。



虫干しは湿度が低く天気のよい日を選びましょう。梅雨明けや湿気の少ない初秋に行うのがよいですよ。
着用する機会を作る
カビは長期間ほったらかしにしている間に発生します。
帯が1番喜ぶ解決策は着用する機会をつくること!
着用することが増えれば、帯から出るカビ臭さにもすぐに気付くことができ大事に至らないでしょう。
外気に触れることで湿気もたまりにくくなり最高のカビ対策になりますよ。
着物帯の手入れの仕方や保管方法をもっと詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をお読みください。
【帯の手入れ】もうカビは怖くない!|まとめ
この記事では、帯にカビが生えたときの対処法と予防法をご説明いたしました。
まずは帯に生えるカビについて解説しました。
- 60%以上の湿度
- 5~35℃の温度
- 酸素
- タンパク質
- 白カビ
表面に現れる初期のカビ。応急処置で除去の可能性あり。 - 黄カビ
白カビを数年放置すると黄カビに。クリーニングが必要。 - 黒カビ
白カビから10年以上たったカビ。クリーニングでも除去困難。
- 帯芯
帯の内側に縫い付けられた布地。湿気がこもりやすく帯芯からカビが生えることが多い。見えないがカビ臭がする。 - 表地や裏地
帯芯のカビが広がって表地や裏地にカビが現れる。進行した黄カビや黒カビの場合が多い。
そして大切な帯にカビを発見したときの対処法は以下の通りです。
対処法
- 自宅で応急処置
・早期発見の場合は、帯を風に当てて湿気を飛ばす。
・1日4~5時間ほど干す×1ヶ月程度
- NG行為
✖ 消臭スプレー
✖ アルコールで拭く
✖ アイロンをかける
✖ 濡れタオルで拭く
- 専門のクリーニング店に依頼
応急処置でカビ臭が消えない場合は帯芯の交換がおすすめ。お店に「洗い張りメニュー」があるか要確認。
最後に、帯にカビを生やさない環境作りについてお伝えしました。
予防法
- 着用後は陰干しする
- 保管はたとう紙で
- 除湿剤を使う
- 定期的な虫干し
- 着用する機会を作る
お嫁入りのときにあつらえたり、母や祖母から受け継いだりすることの多い思いのこもった大切な帯。
もしカビが生えてしまったら、正しい方法で対処しましょう。
そして何よりもタンスに入れたままでカビを生やしてしまわないように、ときどきは身につけてお出かけしてみるのはいかがですか?
きっと帯たちも喜ぶことでしょう。
着物帯全般のお手入れは、下記の記事で詳しく紹介しています。
ぜひご覧ください。
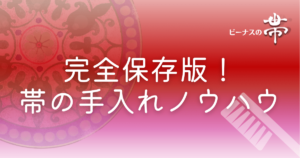
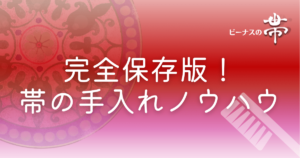
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。





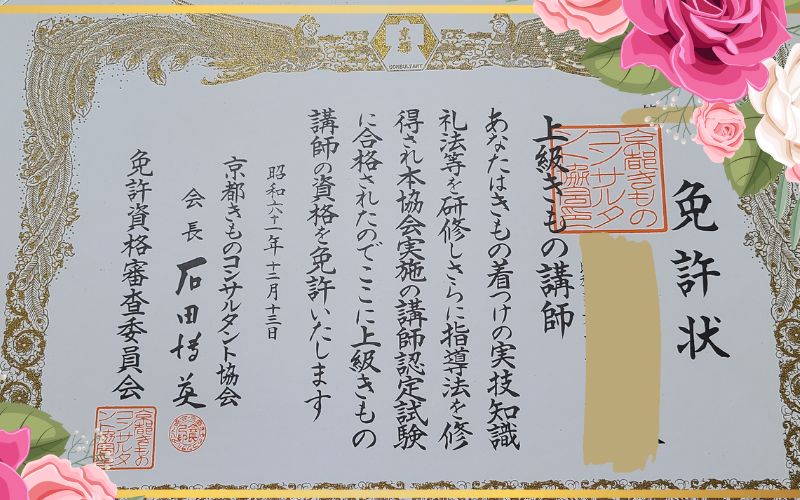

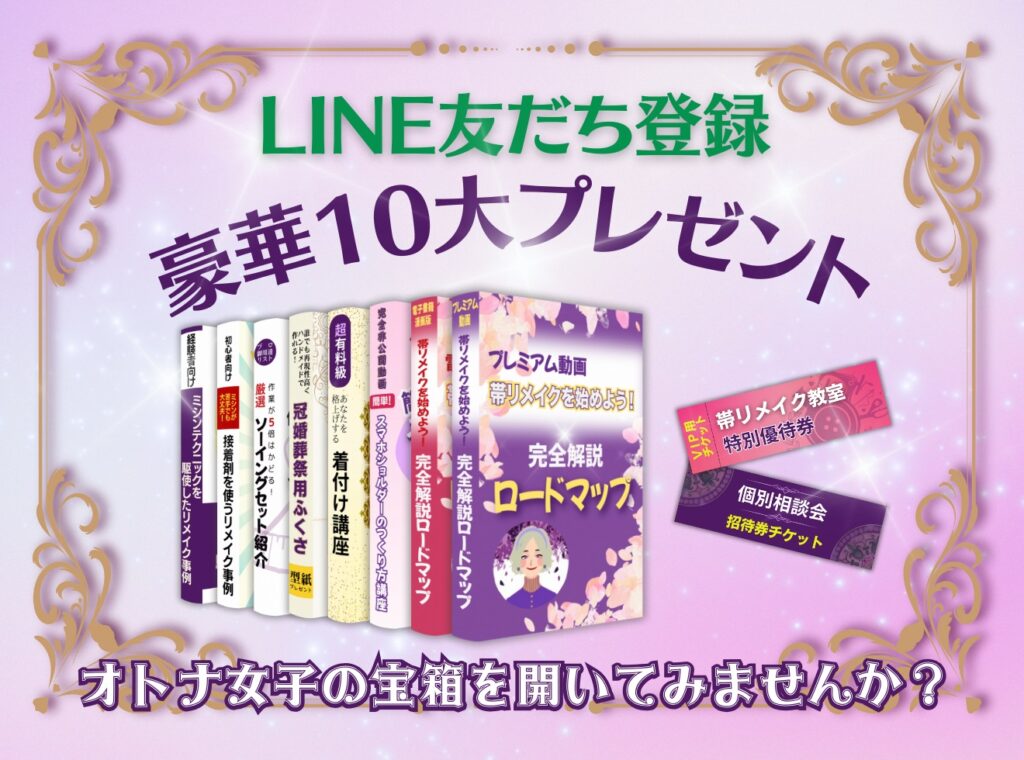


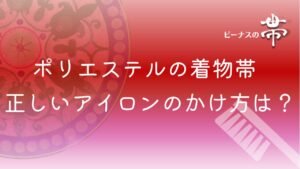


コメント